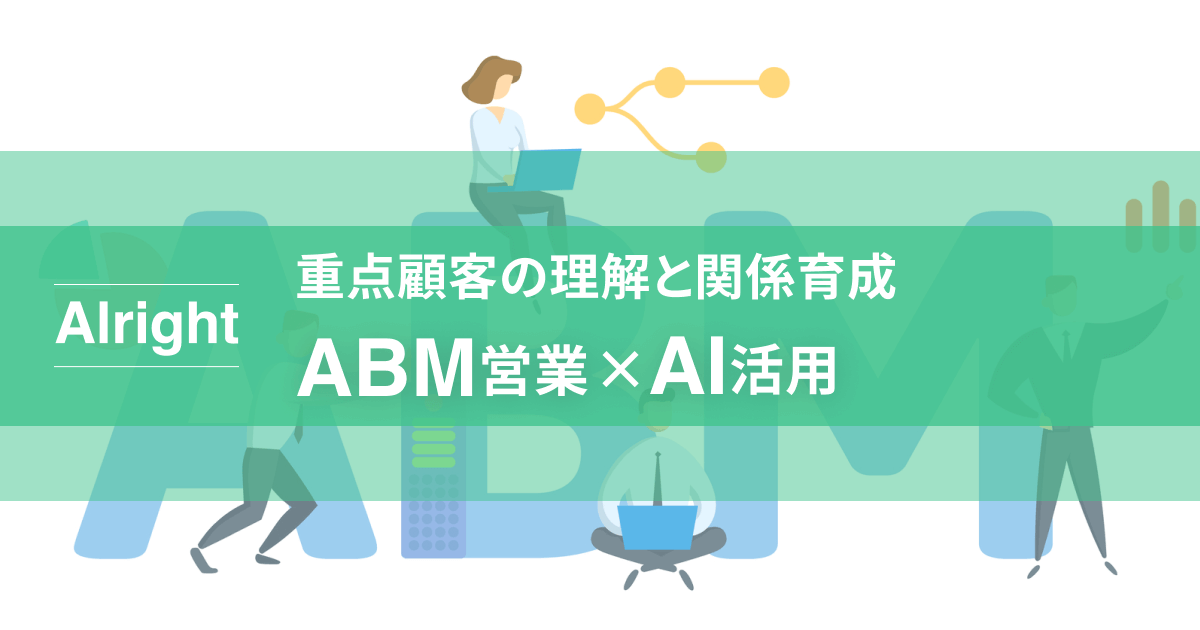1. 営業の時代は「数」から「関係」へ ABMという考え方の広がり
営業の現場で、こんな言葉を耳にする機会が増えていませんか?
「数を追うより、関係を深めるほうが成果につながる」
少し前まで、営業の生産性といえば「どれだけ多くのリードを追いかけるか」「いかに短期間で商談化できるか」が主な指標でした。
しかし、顧客の購買プロセスが複雑化し、意思決定者も増えた今、一度きりの成果ではなく長く付き合える関係をどう育てるかが問われる時代になっています。
その流れの中で注目されているのが「ABM(アカウント・ベースド・マーケティング)」という考え方です。
マーケティングという言葉が入っていますが、実際の主役は営業。
リードを大量に追うのではなく、「重要な顧客を手厚く理解し、継続的に成果を育てる営業スタイル」がABMの本質です。
たとえば、ある企業が自社のサービスを導入してくれたとします。
その瞬間がゴールではなく、「この会社と次に何を一緒に作れるか」「どんな価値を増やせるか」を考え続けること。
これこそがABM営業の思想です。
そして、この理解を深める営業を支えるのがAIです。
AIは、顧客のニュースや決算、SNSでの発言、業界の動きを瞬時に読み取り、営業が気づかない小さな変化まで拾い上げてくれます。
つまりAIは、「人が築いた信頼関係を、データで支えるパートナー」なのです。
ABMは決して特別な戦略ではありません。
むしろ、営業がずっと大切にしてきた人と人との関係を、AIの力で再現し、広げる方法と言えます。
本稿では、そんな「重点顧客を深く理解し、AIで関係を育てる営業」の実践法を解説していきます。
2. ABM営業とは何か 重点顧客営業を仕組みで強くする
ABM営業とは、一言でいえば 「限られた大事な顧客に、より深く、より長く関わるための営業の仕組み」 です。
従来の営業が「数を追う」戦い方だとすれば、ABMは「深さを設計する」戦略。
どの企業に力を入れるのか、その企業の中で誰と関係を築くのかをあらかじめ設計し、チーム全体で動きをそろえていきます。
たとえば、トップ100の重点顧客リストを持つ企業であれば
- 「この会社は今どんなテーマに関心があるのか?」
- 「誰が決裁を握っていて、どの部門が鍵を握るのか?」
- 「どの部署と一緒に取り組めば長期的な関係を築けるのか?」
こうした情報を整理し、アカウント単位で戦略を描くのがABM営業の基本です。
ここで大切なのは、ABMを個人プレーの延長にしないこと。
従来の営業では、担当者の勘や経験が成果を大きく左右していました。
ABM営業ではそれをチーム全体で共有し、「信頼関係をどう再現できるか」を仕組み化していきます。
つまり、営業一人ひとりの関係構築スキルを組織の資産に変えていく考え方です。
また、ABMはマーケティングやカスタマーサクセスとの連携が前提になります。
マーケが顧客との最初の接点をつくり、営業がその関係を深め、CS(カスタマーサクセス)が成果を維持・拡張する。
この三者が連携して初めて、ABMの循環が成り立ちます。
ABMと従来営業のちがい
| 観点 | 従来の営業 | ABM営業 |
|---|---|---|
| 対象 | 多数の見込み顧客 | 重点顧客(数十〜数百社) |
| 主な目的 | 商談・受注の獲得 | 長期的な関係と共創 |
| 成果指標 | 案件数・受注率 | 関係スコア・アップセル率 |
| 営業の中心 | 個人(担当者ごと) | 組織単位(チームで支援) |
ABM営業を実践する企業では、「数を追うのではなく、1社にどれだけ深く入り込めたか」を成果として評価します。
たとえば「1社で新しい部署と関係を築けた」「決裁者との対話が定期化した」といった動きも、立派な成果として記録されます。
💬ワンフレーズで言うなら:
「ABM営業とは、“1社を深く理解することで10社分の成果を生む営業スタイルである」
AIの登場によって、この深く理解する力を誰もが発揮できるようになりました。
次のセクションでは、AIがどのようにこの重点顧客営業を支え、「人の勘」から「データで見える関係構築」へ進化させているのかを見ていきましょう。
3. AIが支える「重点顧客営業」の3ステップ
ABM営業を実践しようとすると、最初にぶつかる壁があります。
それは「深く理解したいけれど、時間が足りない」という問題です。
どんなに優秀な営業でも、数十社の重点顧客のニュース、決算、動向、人事、SNS発言まで全部追うのは至難の業です。
そこで頼りになるのがAI。
AIは、営業の気づきの瞬間を生み出すために、膨大な情報を背景で整理してくれます。
AIをうまく活用するには、ABM営業のプロセスを次の3ステップで考えるとわかりやすいでしょう。
ステップ① ターゲット選定:AIで「伸びる関係」を見極める
まずは、どの企業に力を入れるかを定める段階。
過去の受注データや商談履歴、業界の変化をAIが分析し、今後関係が広がりそうな企業を見つけ出します。
たとえば、AIにこんなふうに頼むだけでも変わります。
この半年で接点が減ったけれど、再提案の可能性がある顧客を5社教えて。AIはCRMやメール履歴、商談メモを読み取り、「連絡が途絶えているが、過去の満足度が高かった企業」「新しい部署が設立された企業」などをピックアップしてくれる。
つまりAIは、追うべき企業ではなく、もう一度育てられる企業を見つけてくれるのです。
これが、ABM営業の第一歩となります。
ステップ② 企業理解:AIで顧客を360°把握する
次に行うのは、ターゲットに決めた企業をとことん理解すること。
AIはここで、まるでリサーチ担当者のような働きをしてくれます。
ChatGPTやGemini、Perplexityに次のようなプロンプトを投げかけると
○○株式会社の直近のニュース・新規事業・採用方針を200字でまとめて。数秒で、公式サイトやニュースリリース、業界動向を要約してくれます。
それを基に営業は、「この企業はいま何に困っていて何を大事にしているか」を整理できます。
さらに、社内のナレッジや過去の提案資料を組み合わせることで、「AI企業カルテ」を作ることも可能です。
このカルテには、以下のような情報が含まれます。
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 最近のトピック | 新規事業の開始、人事方針の変化など |
| 関心テーマ | サステナビリティ、人材育成、コスト最適化など |
| 社内のキーパーソン | 意思決定者と周辺の影響人物 |
| 提案のポイント | 過去に響いたキーワード、NGワード |
| 次の打ち手 | 提案時期、連絡チャネル、推奨テーマ |
このカルテをチームで共有するだけで、誰が担当しても「同じ理解からスタートできる」状態になります。
つまりAIは、顧客理解をチーム共通言語に変える役割を果たします。
ステップ③ 提案最適化:AIが話す順番まで設計する
ABM営業で成果を左右するのは、どんな提案をするかよりも、どんな順番で話すかです。
AIは商談ログやメール文面を読み込み、顧客が反応したキーワードや感情の変化を分析できます。
たとえばAIが以下のような示唆を出してくれることもあります。
「この顧客は“価格”の話より、“社員教育”という切り口に強く反応しています」
「決裁者は“ROI”という言葉より、“将来の人材確保”の話に共感していました」
こうした言葉の温度を掴むことで、営業は提案の切り口を変えられる。
そしてAIは、次回の商談資料をその傾向に合わせて自動生成することも可能です。
いわば、AIが営業の「話す順番」を一緒に考えてくれる存在になるのです。
この3ステップをAIと組み合わせることで、営業は追いかける時間を減らし、向き合う時間を増やすことができます。
つまりAIは、数字を管理するツールではなく、関係を育てるための同僚なのです。
次のセクションでは、こうした仕組みをどう現場に落とし込むのか、実際のABMオペレーションやツール連携の例を紹介していきます。
4. 実装例:AIが営業の勘を見える化する
ABM営業をAIで進めようとすると、よく出てくる悩みがひとつあります。
「ウチ、CRMとかSFAがちゃんと動いてないんだけど、それでもできるの?」という質問です。
結論から言うと、可能です。
しかも、そこから始めるのがちょうどいいのです。
AI導入の第一歩は「感覚をデータ化すること」から
多くの営業現場には、まだバリバリ動くCRMやMA(マーケティングオートメーション)はありません。
Excel、名刺、メール履歴、商談メモなど、そういった情報が点在している状態です。
でも実は、AIにとってはそれで十分。
たとえば、ChatGPTにこんなふうに聞くだけでも立派な一歩になります。
この5社の商談メモを読んで、共通して顧客が不安に思っている点を3つ教えて。営業の感覚としては経験だったものが、AIによって言語化されたパターンとして浮かび上がる。
これが勘の見える化の第一歩です。
つまりAIは、CRMが整っていなくても、人の頭の中にあるナレッジを引き出してくれる存在なんです。
実際には、顧客の名称や価格など、機密事項にあたる情報を伏せた状態で、AIに相談するなど、いくつかの留意事項がありますが、今回はそういったセキュリティ・コンプライアンスに関わる話には触れません。
CRMやSFA、MAといったツールを利用していなくても、AIとコミュニケーションを積み重ねることで、ABM営業は始められるという点だけ覚えておいてくださいね。
CRM/SFAが整っている場合:AIが「整理と提案」を自動化
もしCRM(Salesforceなど)やSFA(営業支援ツール)が稼働している場合は、AIの活躍範囲が一気に広がります。
- 活動履歴の要約:AIが過去の商談記録を読み取り、「関係の温度」や「次に話すべきテーマ」をタグ化。
- ABMダッシュボード:企業ごとに「接点の深さ」「決裁層到達率」「共感トピック」などを自動集計。
- 提案資料の最適化:過去の成功提案をもとに、AIが新しい商談用の資料をカスタマイズ。
たとえば、Salesforceと連携したAIアシスタントにこう指示すると
A社との直近3回の商談内容を要約して、次の打ち手を3パターン提案して。たった数秒で、「提案を拡張する」「他部署に紹介を依頼する」「カスタマーサクセスと連携する」といった具体策が出てきます。
つまりAIは、データを整理するツールではなく、打ち手を考える相棒として機能するのです。
CRMがなくても、できることは多い
それでも、現場には「うちはCRMなんて使ってない」というチームも多いでしょう。
その場合は、無理に大掛かりな導入をせず、まずはAIメモアシスタント的な使い方から始めてみるのがおすすめです。
- 商談メモをChatGPTに投げて「要約+次の一言」を出してもらう。
- 名刺交換した相手の会社をPerplexityに調べてもらい、「次の訪問時の話題」を探す。
- チームで共有したい「お客様の一言」や「気づき」をAIにまとめてもらう。
こうした小さな実践を積み重ねるうちに、AIが拾ってくれた言葉の変化や共通の関心テーマが蓄積され、気づけばそれがCRMの原型になっていきます。
データが営業を縛るのではなく、営業を助ける
AI活用というと「データ入力が大変そう」と構えてしまう営業も少なくありません。
でも本来、AIはデータを整えることが目的ではなく、営業の勘を裏づけるための仕組みです。
たとえば、AIが以下のようなさりげない提案をしてくれるだけで現場は助かります。
「この3社は“社員の定着率”という言葉に反応しています。次回提案ではそのキーワードを入れてみましょう。」
こうした気づきが積み重なると、なんとなく距離が近い気がするという直感を、チーム全体で再現できるようになります。
AIは、経験を置き換えるのではなく、経験を共有できる形に変えるツールなのです。
ABM営業を支えるAIの価値は、「全データを統合すること」ではなく、「人の関係性を可視化し、次の行動を考える手がかりをくれること」にあります。
CRMやMAの整備が進んでいなくても問題ありません。
営業ノートでも、日報でも、顧客のちょっとしたメッセージでもいい。
それをAIに見せて「気づきを教えて」と聞くところから始めてみましょう。
AIは、営業の勘と経験を磨く鏡のような存在です。
そこから、ABM営業=「関係を設計する営業」への第一歩が始まります。
5. ABM営業における共感データの活かし方
ABM営業を進めていくと、数値やデータだけでは見えない人の温度に気づくようになります。
商談で相手の表情が少し緩んだ瞬間、メールで「ちょうどそれ考えていました」と返ってきたとき、その小さな反応の積み重ねが、実はAIが扱う共感データになります。
「共感データ」とは、相手の心が動いた記録
共感データとは、相手がどんな言葉や話題に反応したかの履歴のこと。
メール、商談メモ、SNSの反応、ウェビナーの質問内容など、営業のやりとりの中には「どんな話題で盛り上がったか」がすでに散らばっています。
AIはそれらを自然言語処理で読み解き、「この人はコスト削減よりも組織づくりという話に反応しやすい」「成功事例よりも裏側の失敗談に共感している」といった傾向を可視化してくれます。
このように、数字では測れない人の反応を見える化することで、営業は「次に何を話すか」「どんな言葉で伝えるか」を考えやすくなります。
共感の連鎖をアカウント単位で再現する
特にABMでは、一人の担当者だけでなく、企業全体で信頼を広げていくことが重要になります。
AIが共感データをまとめてくれることで、「誰が、どんな価値観に共感しているか」をチームで共有できるようになります。
たとえば:
- 技術部門は性能向上に共感している
- 経営層はリスク回避の話に共感している
- 管理部門は業務効率化に共感している
これをもとに営業チームが物語を作り直せば、同じ製品・サービスでも、部署ごとに響くストーリーを持つ提案ができます。
つまり、AIは「共感をデータで橋渡しする」存在。
個人の関係構築を、組織的な関係づくりへと広げてくれるのです。
6. 業界別ショートケース:ABM営業×AI活用のリアルな広がり
ABM営業は、大企業のマーケティング部門だけのものといった印象を持たれがちですが、実際には、営業現場から少しずつ浸透している動きが見られます。
ここでは、AIを取り入れながら重点顧客との関係づくりを進めている代表的な業界の例を紹介します。
IT・SaaS業界:導入フェーズ別の提案をAIが支援
IT・SaaSでは、顧客の利用フェーズによって提案内容が大きく変わります。
AIは、契約直後・運用中・更新前といったフェーズごとに商談記録を分析し、「次に話すべきテーマ」や「紹介すべき事例」を自動で提案。
たとえば「この顧客は導入支援の記事に反応しているため、活用研修の提案を優先」といったように、AIが熱量の高いテーマを教えてくれます。
営業は、そのヒントをもとに、関係を次のステージへ育てていきます。
製造業:サプライチェーン全体で関係を可視化
製造業では、一社との取引が複数拠点・部門にまたがることが多く、「どこがキーマンで、どこが影響力を持つか」が見えづらいという課題があります。
AIは、商談ログやメールの宛先情報をもとに、関係ネットワークをマッピング。
どの拠点と接点が多いか、どの部門との距離が開いているかを視覚的に示します。
これにより、営業は抜けていた関係に気づけるようになり、結果的にサプライチェーン全体の信頼構築が進みます。
不動産業界:法人顧客との関係スコア管理にAIを活用
不動産業界では、物件提案や契約更新のタイミングを逃さないことが重要です。
AIは、過去のやりとりや契約サイクルを学習し、「そろそろ提案しておきたい」「担当変更のタイミング」などを営業に通知。
特にBtoB賃貸や施設運営などでは、人間関係を維持するタイミング管理が成果に直結します。
AIは、こうした細やかなフォローを支える影のパートナーとして機能します。
小売・EC業界:パートナーとの共感軸をAIが抽出
小売・ECの世界では、ブランドや販売パートナーとの共同施策が欠かせません。
AIはSNSやレビューを解析し、「どんなテーマに共感が集まっているか」を把握。
「サステナブル」「地域連携」「Z世代」など、共感の軸を可視化します。
そのデータをもとに、営業とマーケが共同でキャンペーンを設計。
つまりAIは、共通の想いを見つけ出し、共創を促す触媒のような役割を果たします。
7. AIが支える関係を育てる営業文化
ABM営業とは、単なる営業手法ではなく、「人と組織の関係を育てる文化」です。
一度の受注で終わるのではなく、顧客と共に歩み、価値を育て続ける。
その過程を仕組みとして整えたものがABMであり、AIはその文化の土壌を耕す存在です。
数字を追う営業から、信頼を積み上げる営業へ
AIを活用することで、営業は数字のためだけに動く仕事から、信頼をデータで再現する仕事へ変わりつつあります。
ニュースや決算を自動で要約してくれるAIもあれば、商談メモから共感キーワードを見つけてくれるAIもある。
それらを使いこなすほど、営業はより人間的な部分に集中できるようになります。
つまりAIは、営業を機械化するのではなく、人の思考と関係構築をより濃くするための相棒なのです。
個の信頼から、組織の信頼へ
これまで、信頼は「担当者が築くもの」でした。
しかし、AIが顧客理解・履歴・感情の機微を記録してくれることで、その信頼がチーム全体に共有され、「組織として信頼される営業」が可能になります。
ABM営業は、まさにその象徴。
個々の営業が築いた関係を、AIが組織の記憶としてつなげていく。
その結果、企業全体が「理解し合えるパートナー」として進化していくのです。
シリーズを通して見えてきた流れ
営業思想・マインドセット特集を通して描いてきたのは、単なるAI活用のテクニックではなく、営業という営みそのものの再定義でした。
この流れは、営業とAIが共に成熟していく物語そのものです。
AIは、営業のあり方を根底から変えつつあります。
けれど、それは「人を置き換える」変化ではありません。
むしろ、人がより人らしく信頼を築くための進化です。
ABM営業は、その象徴的な形。
AIが整理し、提案し、思い出させてくれるおかげで、営業は再び「人と向き合う仕事」へと戻っていく。
これからの営業に求められるのは、テクノロジーの巧さではなく、AIと共に関係を育てる姿勢そのもの。
数字の裏にある人の想いを読み取り、信頼を積み重ねていく。
それが、AI時代の営業文化であり、次の10年を生き抜く力になるとAlrightは信じています。
 無料相談
無料相談