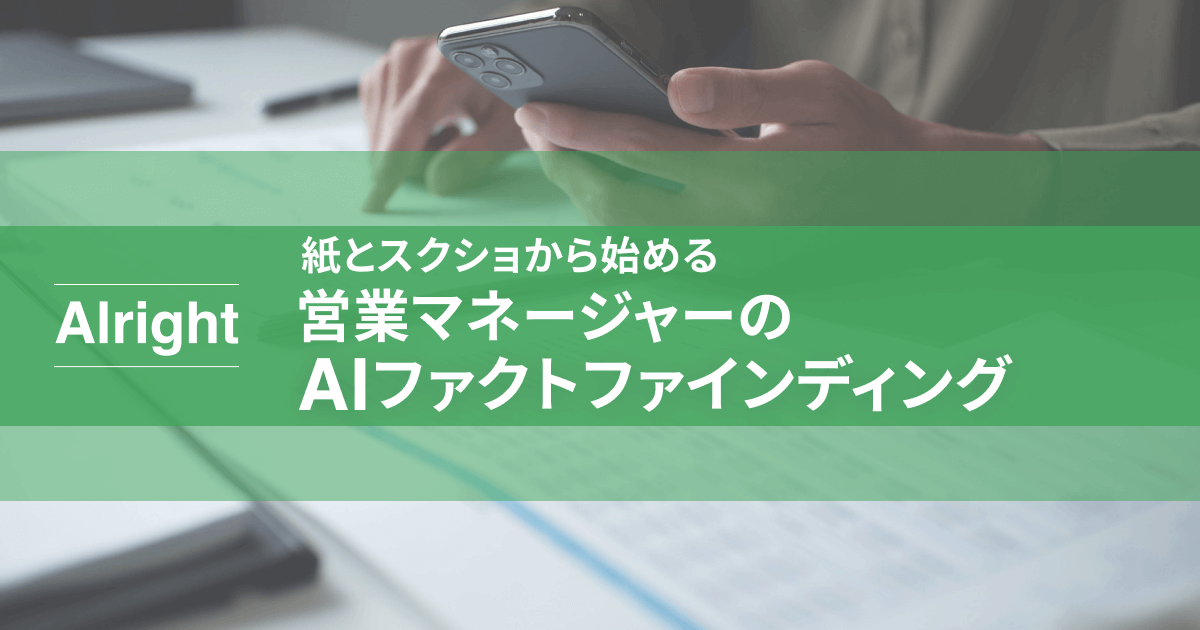1. 営業マネージャーにとってのファクトファインディング
営業マネージャーにとって、部下の提案をレビューする場面でよく直面するのが「説明が感覚的すぎて、判断のしようがない」という問題です。
「お客様はたぶんこう思っているはずです」「競合はおそらくこんな動きをしているでしょう」
そうした推測や印象ばかりが積み上がると、指導も評価も曖昧になってしまいます。
一方で、顧客の実際の発言や数値データといったファクトが揃っていれば、マネージャーはすぐにレビューの論点を見極められます。
「この課題は事実として確認済みだね」「ここはまだ推測だから次回検証しよう」と、指導がスピーディーかつ具体的になるのです。
つまりマネージャーにとってのファクトとは、単なる証拠の積み上げではなく、チーム全体の成果を再現可能にするための仕組み化の材料なのです。
ここで強調したいのは、こうしたファクトの整理やレビューは必ずしも高度なSFAやCRMが必要ではないということです。
極端に言えば、ホワイトボードに書いたメモをスマホで撮影してAIに渡すだけでも十分始められるのです。
AIはあなたの書記係として、紙やスクショから事実を抽出・整理してくれます。
本記事では、SFAやCRMといった営業マネジメントツールを利用せずに、営業マネージャーが簡単にファクトファインディングを実践できる手法を解説していきます。
2. 個人営業とマネージャー視点の違い
営業パーソンがファクトファインディングを行う目的はシンプルです。
自分の提案に説得力を持たせるための証拠を集めること。
顧客の発言や市場データを根拠に添えることで、「この提案は信頼できる」と相手に感じてもらえるようにするのが主眼です。
しかしマネージャーの立場では、ファクトの扱い方は大きく変わります。
個人の提案を強くするだけでなく、チーム全体で成果を再現できる状態にすることが求められるからです。
そのためには、ファクトを「共通言語」や「評価軸」として整理していく必要があります。
たとえば「課題が事実として確認できているか」「関係者の発言に証拠があるか」といった観点を揃えておくと、誰がレビューしても同じ基準で判断できます。
逆に、証拠が揃っていない状態でレビューを続けてしまうと、ナレッジが属人化し、個々人の経験や勘に依存してしまいます。
これでは新人教育や横展開も難しく、マネジメントの負担は増す一方です。
合言葉はシンプルです。
「証拠がなければレビューしない」。
このルールを徹底することで、レビューが形式ではなく実効性を持つようになります。
3. マネジメントでの活用シーン
マネージャーがファクトファインディングを取り入れるとき、大切なのは「どんな場面で活用するか」を明確にすることです。
ここでは代表的な4つのシーンを整理してみましょう。
1. 提案レビュー
部下の提案をレビューする際には、Evidence Card(エビデンスカード)を必ず添付させます。
案件名、課題の事実、関係者の発言などを簡単に書き出した1枚の紙(もしくはスプレッドシート)で十分です。
これがあるだけでレビューは「感覚」ではなく「事実ベース」で進行でき、議論のブレを防げます。
2. 案件進行管理
案件が進むたびに「誰が・いつ・何を承認したのか」をファクトログとして残しておきます。
最初はノートやメモでも構いません。
大切なのは「承認の痕跡」が形として残っていること。
これにより後から振り返っても、意思決定の過程をたどれるようになります。
3. 戦略立案
過去の案件から集めたファクトは、戦略会議での判断材料にもなります。
「どんな理由で失注が多かったのか」「どんな条件のときに受注が増えたのか」
これらを紙やExcelでリスト化してAIにまとめさせれば、すぐに全体像が見えるようになります。
4. 育成・1on1
部下との1on1やフィードバックも、ファクトをベースに行うことで説得力が増します。
「あなたの提案は弱かった」ではなく「この顧客の発言が根拠として不足していた」と具体的に伝えられるため、改善点が明確になり育成効果も高まります。
このように、Evidence Cardとファクトログというシンプルな仕組みを用意するだけで、レビュー・管理・戦略・育成といったマネジメントの主要シーンが一気に「事実ベース」で回り始めます。
4. 最低限のフォーマットで始める
ファクトファインディングをマネジメントに取り入れると聞くと、つい「専用のシステムやツールが必要なのでは?」と思いがちです。
ですが実際には、紙とスマホ、あるいは簡単なExcelやスプレッドシートだけで十分始められます。
ここで大切なのは「誰でもすぐに書ける/残せる」というシンプルさ。
完璧なフォーマットよりも、チーム全員が習慣として運用できることを優先すべきです。
Evidence Card(提案レビュー用)
提案をレビューするときに添付する1枚の整理シートです。最小限で以下の項目を押さえれば機能します。
- 案件名
- 顧客/関係者
- 課題の事実(顧客の発言や数値)
- 制約条件の事実(予算・期日・既存ベンダーなど)
- 提案の肝(根拠と差別化ポイント)
- 未確認事項(次回質問すべき点)
👉 ポイント
ホワイトボードに書いて撮影した写真でも良し、紙に手書きしても良し。
要は「事実を見える形で1枚にまとめる」ことが目的です。
ファクトログ(時系列メモ)
案件の進行や意思決定の履歴を残すためのメモです。
形式は自由ですが、以下のような最低限の欄を揃えておくと便利です。
- 日付
- 記録者
- 出来事
- 区分(事実/推測/感情)
- 次アクション
👉 ポイント
これもノートに書いて写真に残すだけでもOK。
慣れてきたらExcelやスプレッドシートで一覧化すると検索や共有がしやすくなります。
この2つのフォーマットを「レビュー必須の前提」として運用するだけで、会議や1on1が一気に感覚頼みから事実ベースに変わります。
5. AIで補助するファクトファインディング
Evidence Cardやファクトログを運用し始めると、どうしても「書くのが面倒」「まとめる時間が取れない」という声が出てきます。
ここでAIを書記係として活用すれば、事実整理の負担を大幅に軽減できます。
ポイントは、AIに「判断させる」のではなく、「整理させる」こと。
つまりAIは提案の中身を勝手に考えるのではなく、人間が記録したメモや資料を事実ベースに並べ直す係として使うのが安全で効果的です。
1. 商談メモの仕分け
手書きメモや議事録をそのままAIに貼り付け、「事実/推測/感情」に分類させます。
📌 プロンプト例
この商談メモを〈事実/推測/感情〉に分類し、事実だけを箇条書きで抽出してください。2. Evidence Cardの下書き
メモやスクショをAIに渡すと、必要な項目に自動で整理してくれます。
📌 プロンプト例
次の議事録からEvidence Cardを作成してください。
未確認事項は「次回確認リスト」としてまとめてください。3. レビュー支援
部下の提案資料を読み込ませ、根拠不足の部分や追加で必要なデータを指摘させます。
📌 プロンプト例
この提案資料をチェックし、根拠が弱い箇所と追加で必要なデータをリストアップしてください。4. 振り返り要約
ファクトログをAIに投げると、次回のアクションや会議用サマリーを自動で整理してくれます。
📌 プロンプト例
このファクトログを要約し、次回会議で確認すべきポイントとアクションリストを作成してください。このように、AIは「紙やスクショから事実を拾って整える」用途に限って使うのがコツです。
これならツール導入なしでも実現でき、ファクトファインディングを無理なく習慣化できます。
6. レビュー会議の進め方
ファクトファインディングを仕組みとして機能させるには、レビュー会議の進め方を型として整えることが欠かせません。
Evidence Cardやファクトログを揃えたうえで、以下の流れを徹底するだけで会議の質は格段に上がります。
会議前の準備
- Evidence Card(A4一枚)とファクトログ(時系列メモ)を必ず提出させる。
- これが揃っていない案件は会議に乗せない、というルールを徹底する。
会議の流れ(15〜30分想定)
1. 事実の確認(3分)
- Evidence Cardに基づき「何が確認済みか」を全員で確認。
- 推測や思い込みを排除する。
2. 論点の特定(5分)
- 事実に基づき「残された課題」「未確認の点」を抽出。
- 必要に応じてAIで要約させるとスムーズ。
3. 選択肢とリスクの検討(5分)
- 複数の打ち手を並べ、それぞれのリスクや制約を洗い出す。
- ファクトログから類似事例を引き出せば、議論が現実的になる。
4. 意思決定&次アクション(5〜10分)
- どの方針を取るのかを決定。
- ToDoは明確に担当者と期限をセットする。
会議後のフォロー
- AIに議事録やファクトログを要約させ、「決定事項」「次回確認事項」を配布。
- Evidence Cardやファクトログは簡単に写真保存しておけば十分。
このように「ファクトが揃っていなければ会議しない」という前提を徹底し、会議の型を回すことで、議論が感覚的にならず、部下の育成や案件推進のスピードも安定していきます。
7. 業界別イメージ
ファクトファインディングはどの業界でも役立ちますが、運用の仕方は業種ごとに少しずつ異なります。
ここでは、紙・スクショ・AIを組み合わせたシンプルな運用を前提に、代表的な4業界のイメージを紹介します。
IT・SaaS
- 解約理由を「事実」として記録し、チームで共有。
- 例:顧客が「使いこなせなかった」と発言→ファクトログに残す。
- AIに複数案件のログをまとめさせると、「解約理由トップ3」がすぐ見える。
製造業
- 品質トラブルの原因や再発防止策をEvidence Cardに整理。
- 例:納期遅延の原因を「部品不足」「ライン停止」と分けて書き出す。
- 写真や現場メモをAIに読み込ませるだけで、原因一覧が完成。
不動産
- 内見時に顧客が実際に発言した一言をファクトとして記録。
- 例:「日当たりはいいけど収納が少ない」→スクショしてログ化。
- 複数案件のログをAIにまとめさせると、提案改善のヒントが浮かぶ。
小売・EC
- 売上データや顧客アンケートを簡単にExcelにまとめ、AIで分類。
- 例:「価格が高い」「在庫がない」といった声をラベル分け。
- 事実ベースの要因を可視化することで、棚替えや販促企画に直結。
このように、業界ごとの実務にファクトファインディングを落とし込むと、「なんとなくの経験則」から「事実ベースの再現可能な判断」へと一気に変わります。
紙やスクショでも十分に回せるので、どの業界でもすぐに取り入れられます。
8. 導入のステップ
ファクトファインディングをマネジメントに取り入れるときは、いきなり大掛かりな仕組みを作る必要はありません。
「紙・スクショ・AI」だけで始める小さなステップを踏むのがもっとも定着しやすい方法です。
Step1:フォーマットを配布
- Evidence Card(A4一枚)とファクトログ(簡単なメモ欄)のひな型をチームに配布。
- Excelやスプレッドシートを使わなくても、紙に印刷して配るだけでOK。
Step2:レビュー会議で必ず使用
- 案件をレビューにかける際は、Evidence Cardを必須にする。
- 「カードがなければ会議に出せない」ルールを作ると自然に定着。
Step3:AIに整理を依頼
- 部下のメモやスクショをそのままAIに投げて、「事実/推測/感情」に整理させる。
- Evidence Cardやファクトログの下書き係としてAIを活用。
Step4:習慣化→ナレッジ化
- 週次の会議や1on1で継続使用し、ログがたまったらAIでまとめてみる。
- これだけで「勝ち筋」「改善点」が浮かび上がり、ナレッジベースに進化する。
ポイントは、最初から完璧を目指さないことです。
「紙に書いて撮ってAIに整理させる」だけでも、十分に事実ベースの運用がスタートできます。
慣れてきたらExcelやCRMに拡張すればよく、まずは軽く始めることが成功の鍵になります。
9. よくある落とし穴と対策
ファクトファインディングを仕組みとして回そうとすると、最初はうまくいかないこともあります。
ここではよくある落とし穴と、その解決策を整理しておきましょう。
落とし穴1:フォーマットが重すぎる
- 欄が多すぎて「結局、誰も書かなくなる」という失敗。
- 対策:最初は必須5項目(案件名/課題の事実/制約条件/提案の肝/未確認事項)だけに絞る。
落とし穴2:AIのそれっぽい推測が混ざる
- AIが自動生成した内容に「もっともらしいけど根拠不明」な情報が入る。
- 対策:必ず「出典を示す」「事実/推測を分ける」ルールを徹底。AIは下書き係にとどめる。
落とし穴3:形骸化して続かない
- 最初は熱心でも、Evidence Cardやファクトログが形だけになり、誰も見なくなる。
- 対策:会議やレビューに「カードがない案件は扱わない」というゲートを設け、運用の必然性をつくる。
落とし穴4:マネージャー自身が書かない
- 「部下にやらせる」ばかりでマネージャーが実践しないと、定着しにくい。
- 対策:マネージャーも1on1や案件レビューでEvidence Cardを活用し、手本を示す。
こうした落とし穴はどれも「完璧を求めすぎる」「運用ルールがあいまい」のどちらかに原因があります。
シンプルに始め、小さな成功体験を積み重ねることが、ファクトファインディングを習慣にする一番の近道です。
10. ファクトを仕組みに落とし込むマネージャーの役割
営業マネージャーにとってのファクトファインディングは、単に部下の提案を強くするための材料ではありません。
チーム全体の成果を再現可能にするための仕組みづくりそのものです。
- 個人営業が集めるファクトは、提案の説得力を高めるための武器。
- 一方マネージャーにとってのファクトは、レビュー・育成・戦略立案の共通言語。
その仕組みを支えるのが、Evidence Cardとファクトログというシンプルなフォーマットです。
これらを「紙に書く→スクショ→AIで整理」の流れで運用するだけで、チームの会議や1on1は一気に事実ベースに変わります。
AIは万能の意思決定者ではなく、あくまで事実を整える書記係。
人間が判断すべき部分を際立たせ、レビューと育成をスピードアップしてくれます。
最初から完璧なシステムは不要です。
紙とスマホからでも始められる。
そこから少しずつ、ExcelやCRMへの発展を視野に入れればよいのです。
ファクトを仕組みに落とし込むことこそが、マネージャーに求められる新しい役割。
感覚や勘に頼らないマネジメントが、成果の安定化とナレッジ共有を同時に実現していきます。
 無料相談
無料相談