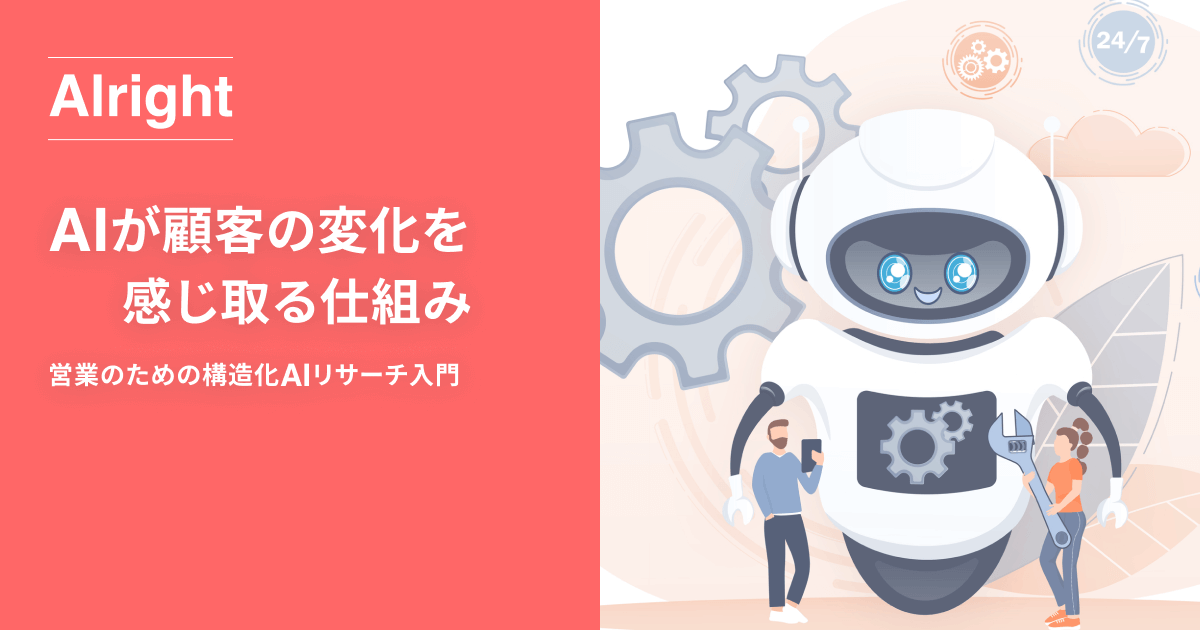1. イントロダクション —— 顧客の変化を構造で捉える
営業の現場でAIを使っていると、「このニュースをどう使えばいいのか?」という瞬間に何度も出会います。
- 製造業の顧客が新工場を建てた。
- SaaS企業がシリーズBの資金調達を発表した。
- 人事異動で決裁者が変わった。
こうした出来事はすべて変化ですが、AIにとっては単なる文字列の集まりです。
重要なのは、その変化を「構造」として読み取れるかどうかです。
Vol.3までのフェーズで、私たちは「顧客属性データ」を整備してきました。
つまり、「誰に話しかけるか」という静的な情報(Who)の部分です。
そしてこのVol.4では、「何が起きたのか」という動的な変化(What’s new)を読み取り、AIが自ら顧客像を更新できるようにしていきます。
AIが読むニュースは、もはや「ネタ」ではありません。
それは「顧客が変化した」という更新信号(Update Signal)です。
私たちがAIにやらせたいのは、ニュースの要約ではなく、「この変化が提案や関係にどう影響するのか?」という構造的な理解です。
たとえば
「A社が新工場を設立した」=生産能力が上がる
→それに伴い教育・品質・物流が課題化する
→だから次の提案は現場教育支援であるべき
このようにニュースを因果の鎖として整理できれば、AIは単なる検索アシスタントではなく、「顧客の変化を感じ取るセンサー」として機能します。
Vol.4では、このセンサーを実現するために、外部のニュース・IR・SNS・求人などの情報をAIが読める構造(YAML/JSON)に整え、さらに営業がすぐ活用できるプロンプトリサーチとして落とし込む手法を解説していきます。
最終的なゴールは、AIがニュースから次に動くべき理由を見つけ出し、「今話しかけるべき顧客」を自動で提案できるようにすることです。
AIに変化を感じさせる。
それが、営業を動的にするということです。
2. 営業にとっての外部情報とは何か —— 仮説補強のための探索
営業がAIを使って情報を探すとき、「どんな企業が動いているか?」よりも先に考えるべき問いがあります。
それは「自分の提案ロジックを強くするには、どんな事実が必要か?」です。
2-1. マーケティングの探索と営業の探索は、似て非なるもの
マーケティングが行う情報収集は「未知の発見」を目的としています。
市場全体を俯瞰し、まだ接点のない顧客を見つけ出す。
だからニュースやプレスリリースを広く拾い、どんな業界で、どんなプレイヤーが動いているかを把握することが重要です。
一方で、営業の探索は「既知の精緻化」です。
すでに商談や関係がある顧客について、今の提案をどう補強できるかを考えます。
つまり、目的は「新規発見」ではなく「仮説の検証・裏付け」。
マーケが広く拾うのに対して、営業は「深く掘る」のです。
2-2. 「顧客探索」ではなく「仮説補強」のためのリサーチ
営業がAIを使ってニュースを読む目的は、「次のネタを探す」ことではありません。
むしろ、自分の提案ロジックを磨くための「エビデンス収集」です。
たとえば、ある製造業のA社に対して「内製化支援サービス」を提案しているとします。
マーケティングなら
「A社 新工場設立」→生産能力増→新規案件検討
営業なら
「A社 新工場設立」→品質教育・物流負担増→現場教育支援が必要
=すでに提案中のテーマに外部裏付けを与える
つまり、同じニュースを見ていても、営業は「ネタ探し」ではなく「仮説補強」に使うのです。
2-3. 外部情報は「提案ロジックの裏づけ」として扱う
AIにニュースを読ませるときのコツは、「顧客起点」ではなく「仮説起点」で投げかける」ことです。
| 探索タイプ | 主な問いかけ | 目的 | 結果 |
|---|---|---|---|
| マーケ的探索 | 「どんな企業が動いている?」 | 新規発見 | 顧客リストが増える |
| 営業的探索 | 「この提案を裏づける根拠は?」 | 仮説補強 | 提案の説得力が増す |
AIに対しても、「A社のニュースを探して」ではなく、「A社に対するこの提案を裏づけるニュースを探して」と依頼するだけで、出力の質がまるで変わります。
AIの検索姿勢を「顧客探索」から「仮説補強」へ変える。
この小さな言い換えが、営業のAI活用を一段深いものにしてくれます。
2-4. 収集すべき情報の優先順位を整理する
とはいえ、営業が一日に扱える情報量は限られています。
すべてをウォッチするのではなく、提案仮説に影響するかどうかを軸に優先順位をつけましょう。
| 情報源 | 主な内容 | 営業的視点での注目点 | 活用イメージ |
|---|---|---|---|
| ニュース/プレスリリース | 製品発表・資金調達・組織変更 | 既存テーマとの因果(教育・品質・人員) | 提案ロジックの裏付け |
| SNS(X/Facebook) | 担当者・文化・発信の傾向 | 意識変化・価値観の兆し | トーン分析・関係構築 |
| IR/決算情報 | 経営方針・リスク・戦略 | 投資・リスク・注力領域 | 提案タイミングの判断 |
| 求人情報 | 新規部署・スキル要求 | 施策の方向性・内製化指向 | 未来仮説の裏付け |
| 口コミ/レビュー | 顧客評価・不満点 | サービス課題・差別化余地 | CS/アフター提案補強 |
つまり「ニュースを追う」のではなく、「提案を補強できる変化を見つける」のが営業の情報探索です。
AIにニュースを読ませるという行為は、広く拾うマーケ的リサーチから深く掘る営業的リサーチへと進化します。
そしてその境界を越える鍵が、次セクションで解説する「AIが読める構造化」です。
3. 外部情報をAIが読める形に整える(YAML/JSON構造)
AIは文脈よりも構造を好みます。
どれだけ良いニュースを拾っても、それがAIにとって読みにくい形で渡されれば、理解されないまま流れてしまいます。
つまり、AIが外部情報を「提案判断の材料」として使うには、ニュースを構造化データとして整えることが欠かせません。
3-1. 構造化の目的は「意味の抽出」と「再利用性」
営業がAIに求めているのは、「要約」ではなく「判断材料」です。
要約は人の代わりに読んでくれるだけですが、構造化はAIが「どこに着目すべきか」を理解するための足場になります。
たとえば以下のような区分があるだけで、AIはニュースを「ただの文字」から「提案に使える信号」へと変換できます。
| フィールド | 意味 | 例 |
|---|---|---|
source | 出典 | 日経新聞 |
date | 発表日 | 2025-10-05 |
title | 見出し | A社、新工場を茨城県に設立 |
summary | 要約 | 関東圏の生産能力強化を目的とした新工場建設を発表 |
impact | 業務・市場への影響 | 教育・品質・物流面での負荷増大が予想される |
relevance | 関連度 | 高 |
tags | キーワード分類 | [製造業, 内製化, 教育支援] |
3-2. YAMLで定義する「AIが読めるニュースフォーマット」
もっともシンプルでAIとの相性が良いのがYAML形式です。
人間が読めて、AIにも解釈しやすいため、営業現場でもスプレッドシートやCRMから自動生成しやすい形式です。
news_items:
- source: 日経新聞
date: 2025-10-05
title: A社、新工場を茨城県に設立
url: https://example.com/a-company-plant
summary: A社は関東圏の生産能力強化を目的に、新工場の建設を発表。
impact: 教育・品質・物流面での課題が発生する可能性がある。
relevance: 高
tags: [製造業, 内製化, 教育支援]AIはこのフォーマットを見るだけで
- どの会社のどんな変化が起きたか
- それがどの領域に影響しそうか
- どれくらい注目すべきか
を一瞬で判別できるようになります。
3-3. impact/relevanceを定義する基準表を持つ
この2つの項目(影響度・関連度)は、ニュース理解の精度を左右します。
人によって基準がぶれるとAI学習の方向もずれます。
そこで、組織内で共有できる「基準表」を設けましょう。
| レベル | 意味 | 判断基準例 |
|---|---|---|
| 高 | 直接的な変化・商談影響がある | 取引企業の戦略・事業変更/新工場・新拠点設立など |
| 中 | 間接的な変化・注視が必要 | 業界トレンド/規制・補助金など |
| 低 | 参考レベル | 社会動向/他業界の一般ニュース |
📌 impactは「何が起きたかの質的要素」
📌 relevanceは「自社・顧客への距離感」
と捉えると整理しやすいです。
3-4. 重複・ノイズを避けるミニルール
ニュース収集を自動化すると、重複や提灯記事(PR系)も多く混ざります。
AIに投げる前に、次のような「下処理」ルールを設けると安定します。
- 同一タイトル類似度が90%以上の記事は除外
- 同一出典+同日記事は1件に統合
- 「PR」「広告」「インタビュー」「ランキング」などの語を含む記事は除外
- URL・日付・出典のいずれかが欠ける記事はAI処理対象外
このルールを守るだけでも、AIが誤ってノイズを学習するリスクを大幅に減らせます。
3-5. YAMLとJSON、どちらを使うか?
AI連携の観点では両方とも利用可能ですが、用途によって次のように使い分けるのがおすすめです。
| 用途 | 推奨形式 | 理由 |
|---|---|---|
| ChatGPTやClaudeなどの会話型AIで直接読み込む | YAML | 人間可読性が高く、プロンプト文中で扱いやすい |
| API連携や自動処理で機械的に扱う | JSON | パース・検証が容易で、スクリプト処理に向く |
たとえば、営業がChatGPTで仮説形成を行うときはYAMLを読み込ませ、CRMやスプレッドシート連携ではJSONに変換して保存するとよいでしょう。
構造を整えるというのは、AIにニュースを「読ませる」ことではなく、「理解の文脈を渡す」ことです。
次のセクションではこの構造を中核に、次章で「顧客属性データとの紐づけ設計」へ進み、AIが「誰に」「なぜ」「いつ」反応すべきかを定義していきます。
4. 顧客属性データとの紐づけ設計
外部ニュースをAIに読ませるだけでは、「それが自社のどの顧客に関係するのか」は分かりません。
AIにとってニュースは「世界の出来事」でしかなく、「自社営業活動における意味づけ」が必要なためです。
その橋渡しをするのが、顧客属性データとの紐づけ設計です。
4-1. 紐づけの基点は「共通キー」を決めること
Vol.3で作成したCustomer_AIViewは、顧客情報を構造的に整えるための社内マスターでした。
この中に、外部情報を関連づけるための共通キー(identifier)を設定します。
よく使われるのは次の3つです。
| 共通キー | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| company_id | A001, B017 | 自社管理ID。CRM連携に最適 |
| domain | a-company.co.jp | Web/SNS/求人サイトとのマッチングが容易 |
| ticker | 6502 | 上場企業のIR/決算情報との連携に有効 |
たとえばニュースのURLや本文中にドメインが含まれていれば、AIは自動的にdomainを照合し、該当する顧客レコードへニュースを紐づけられます。
4-2. Customer_AIViewに外部データ列を追加する
既存の顧客マスターに、外部ニュースとの関係を表す列をいくつか加えます。
最小構成は次のとおりです。
| company | region | industry | last_news | relevance | impact_tags | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A社 | 関東 | 製造業 | 新工場設立(茨城) | 高 | [教育, 品質, 物流] | 2025-10-05 |
| B社 | 東京 | IT | クラウド基盤刷新 | 中 | [セキュリティ, DX] | 2025-09-28 |
last_newsとrelevanceは、AIが「提案優先度」を判断する際の核となる情報です。
4-3. 「更新信号」から「優先度スコア」へ
外部情報は「変化の信号」にすぎません。
その信号を、AIが行動判断に使える「スコア」へと変換します。
priority_score = (0.4 × relevance) + (0.3 × recency) + (0.2 × fit_industry) + (0.1 × intent_signal)| 要素 | 説明 | スコア例 |
|---|---|---|
| relevance | 顧客にどれだけ関係する変化か | 高=1.0/中=0.6/低=0.2 |
| recency | どれだけ最近の情報か | 7日以内=1.0/30日以内=0.6/90日以内=0.3 |
| fit_industry | 業界適合度 | 一致=1.0/類似=0.7/遠い=0.3 |
| intent_signal | 購買意図を示す要素(求人・資金調達など) | 有=1.0/無=0.5 |
このスコアを使えば、AIは「どの顧客のニュースを優先して分析すべきか」を自動で判断できます。
ChatGPTやGeminiにこの構造を読み込ませれば、優先度上位3社の提案更新案を自動生成することも容易です。
4-4. Google スプレッドシートでの実装例
現場でもっともシンプルなのは、スプレッドシートをCRM代わりにしてAIが参照できる形にしておく方法です。
=ARRAYFORMULA(
IF(LEN(Customer_Master!A2:A),
Customer_Master!A2:F,
"")
)これにより、マスターの更新内容がCustomer_AIViewにリアルタイムで反映されます。
外部ニュースデータをApps ScriptやZapierで自動追記すれば、AIが常に最新の顧客状況を参照できるようになります。
4-5. 【最終版】Customer_AIView(Vol.4拡張版)
ここまでで扱った「静的属性」と「動的属性」を統合した最新版が以下です。
Vol.3で整えた「顧客の骨格」に、ニュースやIRなど外部の「変化信号」を追加することで、AIが誰が・どのくらい変化しているかを自律的に判断できるようになります。
| 英語ラベル | 日本語項目名 | 内容例 | 解説 |
|---|---|---|---|
company_id | 顧客ID | A001 | 自社CRM/スプレッドシート連携のための一意キー。 |
company | 企業名 | A社 | 顧客単位の分析中核。日本語表記のままで可読性を保つ。 |
industry | 業種 | 製造業 | クラスタリング・トレンド集計時に必須。擬似マスターで統一。 |
scale | 規模 | 中堅 | スタートアップ/中堅/大企業など固定語彙で管理。 |
region | 地域 | 東京 | 都道府県レベルで標準化し、表記ゆらぎを防止。 |
contact | 担当者 | 田中 | AIが提案書やメール生成を行う際の参照項目。 |
status | 商談ステータス | 提案中 | 商談フェーズを定義(例:初回面談/提案中/成約/失注)。 |
sales_amount | 年商 | 2,000,000,000 | 数値変換でスコア算出に利用可能。 |
employees | 従業員数 | 200 | 規模感や導入リソース見積もりに使用。 |
years_relationship | 取引年数 | 3 | 信頼度スコアやリピート率推定に活用。 |
issue | 顧客課題メモ | 品質改善の提案希望 | AIが提案文を組み立てる際の背景情報。 |
domain | ドメイン | a-company.co.jp | Web/SNS/求人データとのマッチングキー。 |
ticker | 証券コード | 6502 | 上場企業とのIR/決算データ連携用。 |
last_news | 最新ニュース | 新工場設立(茨城) | 最新の外部トピックを記録。 |
relevance | 関連度 | 高 | 顧客課題や取引領域への影響度を定義。 |
impact_tags | 影響タグ | [教育, 品質, 物流] | impactの要素をトピック化しタグで保持。 |
updated | 更新日 | 2025-10-05 | 最終ニュース登録日を自動記録。 |
recency | 新規性スコア | 1.0 | 情報の鮮度(7日以内=1/30日以内=0.6など)。 |
fit_industry | 業界適合度 | 0.8 | ニュースの内容が業界にどれだけ合致するか。 |
intent_signal | 購買意図シグナル | 1.0 | 求人・資金調達・プロジェクト開始などを検出した場合に加点。 |
priority_score | 優先度スコア | 0.92 | relevance+recency+fit_industry+intent_signalの加重平均。 |
✅ この拡張版によって、AIは「顧客属性×外部変化」を同時に読み込み、提案更新や再接触のタイミングをスコアベースで自動判断できるようになります。
4-6. 紐づけ設計がもたらす3つの効果
- 顧客別に変化が可視化される→「どの顧客でどんな変化があったか」が一目で分かる。
- AIの分析精度が上がる→ニュース単体ではなく、顧客文脈で解釈できる。
- 営業アクションが自動化できる→「優先度が上がった顧客に再提案」などのトリガーを設定可能。
ニュースを「どこで拾うか」よりも、「誰のデータに結びつけるか」が、AI営業設計の分水嶺です。
これで、外部情報が「顧客構造の外側」ではなく、「提案行動を動かす内部信号」として機能するようになります。
次のセクションでは、ここで定義した「更新信号」をどうやってAIに拾わせるか。
Deep SearchではなくQuick Prompt Searchで嗅ぎ取る方法を解説します。
5. Deep SearchではなくQuick Prompt Searchの思想
営業がAIを使って情報を探すとき、必要なのは「完璧な答え」ではなく「即応できる仮説」です。
それが、リサーチAIを「深堀り型」ではなく「即応型」として設計すべき理由です。
5-1. Deep Searchは研究用、Quick Searchは現場用
AI検索では「Deep Search」という言葉がよく使われます。
モデルがウェブ全体を横断的に解析し、複数の出典を組み合わせて高度な回答を生成する手法です。
Deep Searchは、確かに精度が高く、背景文脈まで整っています。
ただし、その代償として「重い・遅い・制限がある」という3つの制約がつきまといます。
| 項目 | Deep Search | Quick Prompt Search |
|---|---|---|
| 主目的 | 網羅的な調査・分析 | 仮説補強・即応判断 |
| 実行時間 | 数分〜十数分 | 数秒〜1分 |
| 成果物 | 詳細レポート | 意思決定のきっかけ |
| 利用頻度 | 1日数回(制限あり) | 毎日・随時 |
| 想定ユーザー | 調査部門・マーケ・経営企画 | 営業・カスタマーサクセス |
営業が必要としているのは、「この提案、今の状況に合ってる?」という1分以内の判断です。
重厚なレポートよりも、小さく速く試せる検索こそが現場には合っていることから、今回のようなケースにおいては、Alrightは従来型のQuick Searchの活用をまずはおすすめします。
5-2. 「深く掘る」より「素早く嗅ぎ取る」
AIリサーチにおける価値は、「深さ」ではなく「感度」です。
ニュースやSNSの変化に反応できる嗅覚を持つことが、営業力を高めます。
AIに求めるのは
- 100%の確証ではなく、行動を決めるための70%の確信
- 調査報告ではなく、判断の引き金になる一文
それがQuick Prompt Searchの思想です。
たとえば、ChatGPTやGeminiで次のようなプロンプトを使えば、営業が「直感的に使える」速さと粒度で結果を得られます。
目的: A社に対する内製化支援提案の仮説を補強するため
教育・品質・サプライチェーン関連の最新情報を3件以内で取得
出力: 出典・URL・要約・関連度
制約: 初期検索3回以内、重複除外、日付明記数秒で、一次情報から3件の有効なニュースを引き出す。
これだけで十分です。
営業が次に話す内容を1段階アップデートできるのなら、それはもうリサーチの完了(営業としての)といえるためです。
5-3. 営業に求められるのは「反応の速さ」と「再検証の軽さ」
営業の情報探索には、スピードと柔軟性が何より大事です。
今日見つけたニュースが、明日には古くなっている世界だからです。
Quick Prompt Searchの運用では、次のような姿勢が基本になります。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 1. 目的を明示する | 「A社提案の補強」「競合動向の確認」など検索の目的を必ず含める。 |
| 2. 出典を明記する | AIの出力にURL・日付・媒体を必ず記録させる。 |
| 3. 検索時間を制限する | 初期検索数を3件以内などで完結させ、再検索しやすくする。 |
| 4. 検証を前提にする | 100%信じず、ChatGPTで内容を再要約・再評価させる。 |
PerplexityやGeminiはこのような即応プロンプトと相性が抜群です。
API経由で自動監視も可能ですが、営業パーソンが直接プロンプトを使いこなすだけでも、日々の提案更新に大きな差が出ます。
5-4. Quick Prompt Searchの実践テンプレート
最後に、営業現場で使えるQuick Searchの基本テンプレートを示します。
あなたは営業担当です。
以下の提案を検証・補強・比較するために、最新の外部情報を3件以内で検索・要約してください。
【提案内容】
A社向け:内製化支援サービス
【リサーチ目的】
教育・品質・サプライチェーンに関する動向確認
【出力形式】
- 出典
- URL
- 要約(150字以内)
- この情報が提案にどう影響するか(補強・反証・比較のいずれか)
制約条件:
- 初期検索数を3件以内
- 同一媒体・同日記事の重複除外
- 出典・日付を明記🔁 ポイント:
「完璧に調べる」ではなく、「今動くために調べる」。
AIはリサーチャーではなく、変化を嗅ぎ取るパートナーです。
この「Quick Prompt Search」を営業の日常に落とし込めば、AIは「資料を作るためのツール」から、「次の行動を決めるセンサー」へと進化します。
次のセクションでは、さらに一歩進んで、このQuick Searchの結果を活用する逆引き型プロンプト設計を解説します。
AIが「仮説を補強する」「反証する」「競合と比較する」という、3方向の探索を自律的に行えるようにします。
6. 提案ロジック起点の逆引きプロンプト
AIにニュースを探させるのではなく、自分の提案ロジックをもとに、AIに検証・補強・比較をさせる。
この視点が、営業におけるAI活用の核心です。
AIが優秀な「ニュースリーダー」から「検証アシスタント」に変わる瞬間、それが、今回紹介する逆引きプロンプトを使ったリサーチです。
6-1. 仮説を持って逆引くという発想
営業の情報探索は、「情報→解釈」ではなく「仮説→情報→再検証」の順序で動きます。
AIを使うときもこの思考構造をそのまま写すことが重要です。
例として、実際のやりとりを見てみましょう。
あなた: 「A社への内製化支援提案を進めています。
教育・品質・物流を課題と仮定しています。
この仮説を裏づける、または否定する最新の情報を直近30日以内で3件探してください。」
AI: 「承知しました。製造業×内製化に関する動向を検索します……」このようにユーザー側が明確な仮説を提示することで、AIは検索ではなく「検証」という行為を実行します。
6-2. 逆引きプロンプトの3パターン
営業がAIにリサーチを依頼する際は、目的に応じて次の3種類のプロンプトを使い分けるのが効果的です。
それぞれに「AIが何を評価すべきか」を明示し、情報の「質」と「信頼性」を判断させます。
💪 パターン①:補強型リサーチ — 提案の根拠を強める
あなたは営業戦略の検証を支援する情報アナリストです。
以下の提案を裏づける外部情報を検索し、信頼性と関連性の観点から評価してください。
【提案内容】
- 顧客: A社(製造業)
- 提案: 内製化支援サービス
- 提案の核: 教育体制構築/品質管理強化/サプライチェーン最適化
【検索条件】
- 対象期間: 直近6ヶ月以内
- 情報源の優先順位: ①公式IR・プレスリリース ②業界専門媒体 ③主要経済メディア
- 件数: 3〜5件(質を優先)
【出力形式】
1. **情報源**: 媒体名/発行元/公開日
2. **URL**: (可能な場合)
3. **要約**: 約300字
4. **提案との接続**: この情報が提案のどの要素(教育/品質/SC)を裏づけるか
5. **信頼性評価**: 5段階評価+理由(一次情報性・実績・発行体など)
【制約】
- 生成系メディア・個人ブログは除外
- 憶測・感想ではなく事実ベースの記事を優先
- 類似内容がある場合は最も一次情報に近いものを採用🎯 狙い:「提案の筋を強化する」「説得力を高める」ための根拠を迅速に集める。
最新LLMではPerplexityやGeminiがこの検索構造に最適です。
⚖️ パターン②:反証型リサーチ — 提案の盲点をあぶり出す
あなたは営業提案のリスク分析を専門とするアドバイザーです。
以下の提案に対し、実現を阻害する可能性のある外部情報を検索し、リスクの種類と重大度を評価してください。
【提案内容】
- 顧客: A社(製造業)
- 提案: 内製化支援サービス
- 想定している前提: 教育投資により品質向上とコスト削減を両立できる
【検索の着眼点】
- コスト面: 内製化による想定外コスト増事例
- 人材面: 教育投資が成果につながらなかった事例
- 品質面: 内製化後の品質低下事例
- 組織面: 外注とのバランス崩壊による失敗事例
【出力形式】
1. **情報源**: 媒体名/発行元/公開日
2. **URL**: (可能な場合)
3. **要約**: 約300字
4. **リスクの種類**: コスト/人材/品質/組織
5. **重大度評価**:
- A:提案の根幹を揺るがす
- B:一部修正が必要
- C:想定内で対策可能
6. **対策の方向性**: このリスクに対して営業としてどう備えるべきか簡潔に提案
【情報源の制約】
- データ・事例を含む記事を優先
- 意見・予測記事ではなく実績ベースを重視
- 学術研究・企業の失敗報告歓迎🎯 狙い:「リスクを見つけて潰す」のではなく、「反証を踏まえて再構築する」。
Gemini+Claudeの組み合わせが、リスクの抽出と分析に非常に強いです。
🥊 パターン③:競合対比型リサーチ — 市場での立ち位置を見極める
あなたは競合分析を専門とする営業戦略コンサルタントです。
以下の提案領域において、競合他社の動向を調査し、自社提案との差別化ポイントを明確にしてください。
【提案内容】
- 顧客: A社(製造業)
- 自社提案: 内製化支援サービス(教育/品質/SC最適化)
- 自社の強み: 製造業特化の教育カリキュラム、品質保証の伴走支援
【調査対象】
- 競合範囲: 内製化支援・製造業コンサルを提供する企業
- 着眼点:
①教育プログラムの内容・期間・費用
②品質管理の手法・ツール
③組織変革支援の体制
④実績・成功事例の公開度
【出力形式】
1. **競合企業名**(特定できる場合)
2. **情報源**: 媒体名/公式サイト/公開日
3. **URL**: (可能な場合)
4. **サービス概要**: 約300字
5. **特徴的な要素**: 強み・独自性
6. **自社との比較**:
- 類似点(共通基盤)
- 相違点(差別化余地)
- 自社が優位に立てる角度
【情報源の優先順位】
1. 公式プレスリリース/IR資料
2. 導入事例・顧客インタビュー
3. 業界専門メディア記事
4. (補足)第三者評価・受賞歴
【制約】
- 不明な箇所は「不明」と明記
- 推測ではなく事実ベースで比較🎯 狙い:競合を「叩く」のではなく、「自社の立ち位置を客観的に見せる」。
Perplexity+NotebookLMの構成が、トレンド整理と比較構造化に最適です。
6-3. 3つのリサーチをどう使い分けるか
AIリサーチは「何を探すか」ではなく、「どの立場で探すか」によって精度が変わります。
以下のようにAIツールを役割で分けると、もっとも効率的に運用できます。
| リサーチタイプ | 狙い | 推奨AI構成 | 使用タイミング |
|---|---|---|---|
| 補強型 | 提案の信頼性を高める | ①Perplexity/Geminiで検索 → ②ChatGPT/Claudeで要約・構造化 | 商談準備/提案書作成時 |
| 反証型 | リスク・盲点を洗い出す | ①Geminiでリスク探索 → ②Claudeで重大度評価・対策提案 | 内部レビュー/ロジック磨き直し |
| 競合対比型 | 差別化・トレンド分析 | ①Perplexityで情報収集 → ②NotebookLMで構造化・比較表作成 | 提案更新/経営報告時 |
💡 「AIを並列ではなく連携で使う」ことが、営業DXの精度を決める。
6-4. 逆引きプロンプトを営業文化に組み込む
この3系統の逆引きプロンプトを、チームの標準フォーマットとして共有しておくと、「思考の再現性」と「知の蓄積」が生まれます。
- 朝会では「反証型」で提案仮説の穴を確認
- 提案会議では「補強型」で裏付けを整理
- 月次報告では「競合型」で市場の変化を可視化
こうしてAIを思考を共にするパートナーとして日常化すれば、営業は「経験に頼る組織」から「検証する組織」へと進化します。
Quick Prompt Searchで「速さ」を、逆引きプロンプトで「深さ」を。
その両輪が揃ったとき、AIはようやく「思考をともにする営業パートナー」になります。
7. まとめ —— AIに顧客の変化を感じさせる
営業がAIと共に歩む時代において、もっとも大きな変化は「情報を集める」ことではなく、情報の意味を再定義する力を手に入れたことです。
AIは、あなたが整えた構造の中で初めて「変化」を理解します。
だからこそ、AIが感じ取る「外部信号」は、あなたの思考の解像度そのもの。
Vol.4で扱った「Quick Prompt Search」と「逆引きプロンプト」は、AIを「リサーチャー」から「共思考者」へと進化させるための二輪駆動です。
🚀 Vol.4の核心メッセージ
| 軸 | 意味 | 使い方 |
|---|---|---|
| 構造 | ニュースやSNSを「信号」として扱う | AIが読める形式(YAML/JSON)で整理 |
| 探索 | 情報を拾うから嗅ぎ取るへ | Quick Prompt Searchで即応判断 |
| 思考 | 仮説から逆引く | 補強/反証/競合の3系統で検証 |
| 更新 | 顧客データと連動 | Customer_AIViewで変化を記録・学習化 |
AIを動かすのではなく、AIに感じさせる。
そのための鍵が、構造化と問いの精度です。
💬 最終チェック —— あなたのAIは、顧客の変化を感じ取れているか?
- ☐ ニュースやSNSなどの外部情報を、AIが読める構造で整理しているか?
- ☐ Quick SearchとDeep Searchを使い分けているか?
- ☐ 「提案ロジック起点」でAIに問いかけているか?
- ☐ 反証・競合情報も「提案材料」として扱っているか?
- ☐ AIが更新した顧客データを、次の提案に反映できているか?
🧩 3秒まとめ
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 思想 | AIは鏡でありセンサー。営業の構造と思考の整い方を映し出す存在である。 |
| 実務 | 静的データと動的データを統合し、Quick Search×逆引きで更新を回す。 |
| 行動 | 速く嗅ぎ取り、深く検証し、AIに変化を学習させる。 |
 無料相談
無料相談