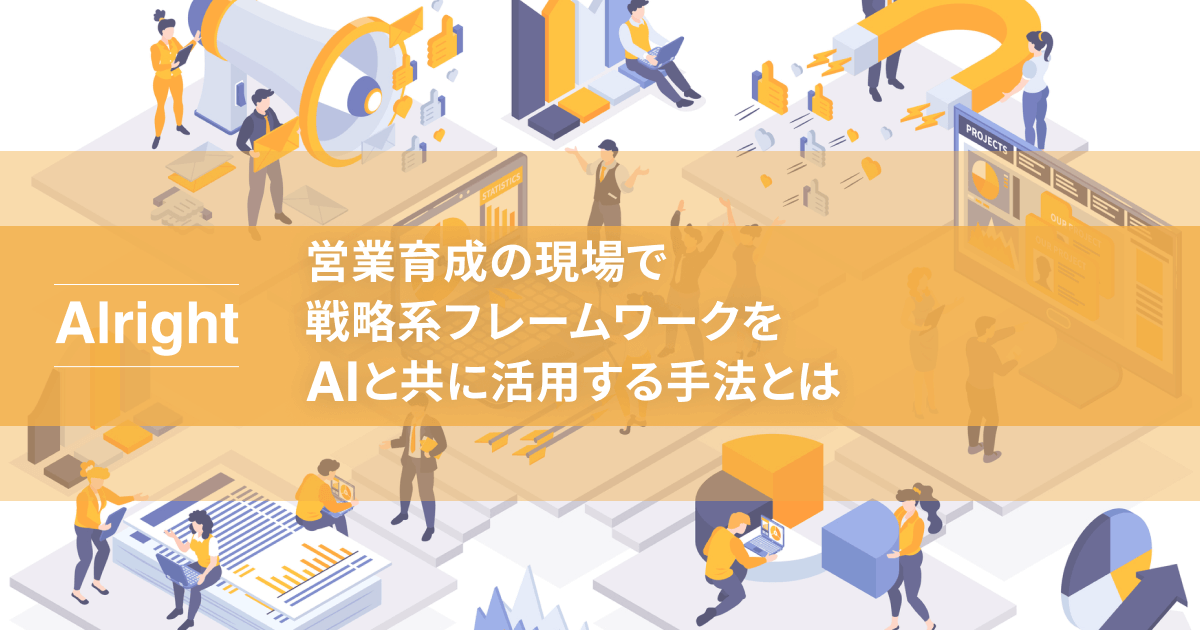なぜ今、営業育成の現場にフレームワークが必要なのか?
1on1、OJT、評価面談といった営業の育成ミーティング。
どれも重要と分かっていながら、「何をどう話すか」「どう結論づけるか」が属人的になりがちです。
背景には、いくつかの変化があります。
- VUCA/BANIに象徴される市場環境の不確実性
- リモートワーク浸透で「偶発的な学び」が減ったこと
- キャリアの多様化により、育成の前提が揃わなくなったこと
こうした環境下で、フレームワークは考えや会話を整理する補助輪として機能します。
ただし大切なのは「理論通りにやること」ではなく、現場に翻訳して使うことです。
さらにAIを組み合わせれば、準備から実施、振り返りまでを効率化でき、育成サイクルを回しやすくなります。
本記事(共通編)では、営業育成全般で土台となる共通フレームワークを整理します。
VUCAやBANIのような環境認識から、PEST・3C・SWOT/TOWSといった戦略思考の基本まで。
次に続く「1on1編」「OJT編」「評価面談編」の理解を深める前提としてご活用ください。
1. VUCA(ブーカ) 共通フレームワーク(環境認識)
歴史
VUCAは、Volatility(変動性)/Uncertainty(不確実性)/Complexity(複雑性)/Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉です。
もともとは1990年代後半にアメリカ陸軍戦略大学(U.S. Army War College)で登場した軍事用語。
冷戦後の国際秩序が急速に変動し、従来の前提では説明できない環境を捉えるために生まれました。
その後2000年代には、リーダーシップ論や経営学の分野で徐々に取り入れられ、「予測困難な状況下で意思決定するための概念」として広がっていきます。
年表で見るVUCAの広がり
- 1990年代後半:米軍で登場、冷戦後の国際環境を説明
- 2000年代:経営学やリーダーシップ論に輸入
- 2010年代前半:グローバル企業や研修で活用が始まる
- 2016年:世界経済フォーラム(ダボス会議)で「VUCAワールド」が話題に→世界的に定着
- 2020年代:コロナ禍やAIの進展で「VUCA時代」が現実のものに
浸透背景
VUCAがビジネスで急速に浸透したのは、社会の急激な変化を整理する枠組みとして分かりやすかったからです。
- グローバル化の加速:競争相手や市場が一気に広がり、不確実性が増大
- デジタル技術の進展:ITやAIの普及で変化のスピードが桁違いに
- リーマンショックやコロナ禍:想定外の外部ショックで計画の前提が崩れる
- 多様なキャリアの台頭:従来の一本道キャリアが崩れ、曖昧な選択が増加
こうした背景から、VUCAは単なる軍事用語ではなく、現代ビジネスを象徴する概念として人材育成や経営戦略に定着しました。
営業育成での使い所
営業組織でもVUCAの要素は日常的に現れます。
- Volatility(変動性):顧客の予算や購買時期が突発的に変わる
- Uncertainty(不確実性):競合の出方が読めず、提案の結果も予測しにくい
- Complexity(複雑性):意思決定に複数部署が関わり、要件が錯綜する
- Ambiguity(曖昧性):顧客自身も「本当の課題」が分かっていない
育成の場では、このVUCAを「自分や部下が成果を出せないのは能力不足だから」と短絡的に解釈しないための免罪符ではなく説明の枠組みとして使えます。
例えば、1on1で「今期の未達はUncertainty要因が大きい」と整理できれば、個人の責任に押し付けず、チームで補完する方策を考えやすくなります。
AI活用例
VUCAは抽象度が高いため、「具体的にどの要素に当てはまるのか?」を可視化できると有効です。
AIを使えば以下のような活用が可能です。
📌 商談ログからVUCA分類を自動生成
以下の商談記録を読み、出来事をVUCAの4要素に分類してください。
・Volatility(変動性)
・Uncertainty(不確実性)
・Complexity(複雑性)
・Ambiguity(曖昧性)
各要素ごとに1〜2行で要約してください。📌 1on1の準備支援
マネージャーが部下との面談前に「この1週間で直面したVUCA要素は何か?」をAIに整理させ、会話の入口として使う。
これにより「何を努力すべきか/何は環境要因か」の切り分けがスムーズになり、心理的安全性も高まります。
👉 VUCAは「成果を出せないのは誰の責任か」を問うのではなく、環境がどう変化しているかを共通認識にするための枠組みであり、営業育成の場では、部下の努力不足に矮小化せず、外部要因を言語化して議論の起点にすることに意味があります。
2. BANI(バーニー) 共通フレームワーク(環境認識)
歴史
BANIは、Brittle(脆さ)/Anxious(不安)/Nonlinear(非線形)/Incomprehensible(不可解)の頭文字を取った概念です。
提唱したのは未来学者Jamais Cascio(ジャメイス・カシオ)。
2020年、パンデミック直後の世界を分析する文脈で提示されました。
従来から使われていたVUCAのフレームでは説明しきれない「社会の心理的ストレス」や「システムの脆さ」を捉えるために登場したのがBANIです。
年表で見るBANIの広がり
- 2020年:Jamais CascioがBANIを提唱
- 2020年〜:パンデミックによる社会システムの脆弱性を説明する枠組みとして注目
- 2021年以降:経営・人材開発の分野でVUCAの後継フレームとして紹介され始める
- 2023年以降:生成AIの急速な普及に伴い、変化の「非線形性」「不可解さ」を説明する概念として再注目
浸透背景
BANIが注目されたのは、VUCAでは捉えきれない現代特有の不安や混乱が増えたからです。
- Brittle(脆さ):グローバルなサプライチェーンが一箇所で崩れると全体が機能不全になる
- Anxious(不安):不透明な環境で人が過剰に不安やストレスを抱える
- Nonlinear(非線形):小さな出来事が想定以上に大きなインパクトを引き起こす
- Incomprehensible(不可解):複雑すぎて人間には理解できない現象が増える
VUCAが「環境変化の外形」を語るのに対し、BANIは人間の感情やシステムの脆さに光を当てたのが特徴です。
パンデミックや地政学リスク、そしてAI普及のように「説明できない変化」に直面したビジネスパーソンの実感に合致し、注目を集めました。
営業育成での使い所
営業現場でもBANIの要素は日常的に表れます。
- Brittle:属人化したノウハウに依存し、担当者が抜けると営業体制が脆い
- Anxious:新規営業が結果を出せず、過剰に不安を抱えてしまう
- Nonlinear:小さなミスが顧客解約につながり、予測以上の損失を生む
- Incomprehensible:複雑な製品・市場構造を新人が理解できず混乱する
育成の場では、BANIを用いて「本人の努力ではどうにもならない構造的要因」を言語化することが重要です。
例えば、「結果が出ないのはAnxious要素が強く、心理的に萎縮しているから」と整理できれば、トレーニングや声かけの方向性が見えてきます。
AI活用例
BANIは抽象的ですが、AIにサポートさせることで「不安や脆さの兆候」を具体的に可視化できます。
📌 日報コメントのBANI分析
以下の営業日報をBANI(Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible)の観点で分析してください。
各要素に当てはまる発言があれば1行で抜粋・分類し、不足する要素は「該当なし」と書いてください。📌 1on1での焦点整理
AIに直近の会話ログを渡し、「部下の発言におけるAnxious(不安)要素が強いか」を判定させる。
これにより、面談では安心感を与えるフィードバックから始める、といった進め方が可能になります。
👉 BANIは、VUCAに比べて「心理的・感情的要因」に焦点があるので、営業育成での活用も「成果の背景にある心の状態をどう読むか」がポイントになります。
3. PEST(ペスト) 共通フレームワーク(思考整理)
歴史
PEST分析は、Politics(政治)/Economy(経済)/Society(社会)/Technology(技術)の頭文字を取った代表的なフレームワークの1つです。
1960年代に経営学やマーケティングの分野で体系化され、企業が外部環境を把握するための基礎的な手法として広まりました。
その後、要素を拡張した「PESTEL(法律・環境を追加)」「STEEP」などの派生形も登場し、グローバル企業やコンサルティングファームの定番分析として定着。
シンプルでありながら、外部要因を整理して戦略や育成の前提を可視化できる点が長く評価されています。
営業育成での使い所
営業育成の場では、PESTを「市場や外部環境の地図」として活用できます。
- Politics(政治):規制変更や補助金政策→「業界全体での営業戦略に影響」
- Economy(経済):景気動向や金利→「顧客予算の増減に直結」
- Society(社会):人口動態や価値観の変化→「購買行動や意思決定者の変化」
- Technology(技術):新しいツールやAI普及→「営業プロセスや顧客期待の変化」
例えば、評価面談や四半期レビューの場で「なぜ今期は数字が伸び悩んだのか?」を議論する際、個人の努力不足ではなくPEST要因に起因している可能性をフレームで説明できます。
この視点を持つだけで、部下へのフィードバックは「叱責」ではなく「次に備える対策」の方向に変わります。
AI活用例
PESTは情報収集に手間がかかるのが弱点ですが、AIを活用すれば負担を大幅に減らせます。
📌 ニュース記事やレポートをPEST要約
以下の業界ニュースをPEST(Politics/Economy/Society/Technology)の観点で分類し、各要素に対応するポイントを1〜2行でまとめてください。📌 四半期レビュー用の「1枚サマリ」作成
AIに商談ログ・失注理由・競合情報を渡し、PESTで整理させる。
「今期はTechnology要素(AI競合の台頭)が商談結果に影響」といった共通認識を持ちやすくなる。
👉 PESTは「代表的な古典フレームワーク」ですが、営業育成に引き直すと環境を個人の責任に押し付けない視点を提供するツールになります。
4. 3C(スリーシー) 共通フレームワーク(思考整理)
歴史
3Cは、Customer(市場・顧客)/Competitor(競合)/Company(自社)の3つの視点から環境を整理するフレームワークです。
1980年代に経営戦略コンサルタントの大前研一氏が提唱したことで広まり、マーケティングや経営戦略の基本モデルとして定着しました。
SWOTやPESTと並ぶ「古典フレーム」であり、特に日本企業の経営戦略や営業戦略の立案において長らく活用されてきた実績があります。
営業育成での使い所
営業育成の場で3Cを使うと、営業活動を「環境」と「自社の強み・弱み」の両面から捉える視点を鍛えられます。
- Customer(市場・顧客):顧客の購買行動や意思決定プロセスを理解する
- Competitor(競合):競合他社の強み・弱み、アプローチ手法を把握する
- Company(自社):自社が提供できる独自価値や不足部分を整理する
例えば、OJTやチームレビューの場で「競合の提案資料はどう違う?」「顧客が重視しているのは価格か機能か?」といった議論を3Cに沿って行えば、営業戦略を「なんとなくの感覚」ではなく、構造的に理解させるトレーニングになります。
AI活用例
3Cの活用は「情報収集と整理」に時間がかかるのが課題ですが、AIで大幅に効率化できます。
📌 競合比較の自動整理
以下の情報を3C分析に整理してください。
・Customer(市場・顧客):顧客の要望・トレンド
・Competitor(競合):競合の特徴・強み・弱み
・Company(自社):自社の提供価値や課題
各Cごとに2〜3行でまとめてください。📌 育成ワークでのAI活用
営業メンバーに日報や商談メモを入力させ、AIに3Cに沿って要約させる。
チームレビュー時に「どの観点が弱いか」を即時確認でき、学習効果が高まります。
👉 3Cは「営業戦略の入り口」として最適なフレームのため、顧客・競合・自社を同時に俯瞰することで、営業が取るべきアクションを環境に基づいて説明できるようになり、育成の場での思考訓練にも直結します。
5. SWOT(スウォット) 共通フレームワーク(実行)
歴史
SWOT分析は、Strengths(強み)/Weaknesses(弱み)/Opportunities(機会)/Threats(脅威)の頭文字を取った戦略フレームワークです。
1960年代にスタンフォード大学の研究プロジェクトで原型が生まれ、1970年代以降に企業経営やマーケティング戦略の場面で広く普及しました。
自社の内部要因(強み・弱み)と外部要因(機会・脅威)を整理することで、戦略を検討する際の基盤として長年使われてきました。
シンプルながらも多様な文脈に適用できるため、今なおもっとも知名度の高いフレームのひとつです。
営業育成での使い所
営業育成の現場では、SWOTを「自己分析と市場認識をつなぐ橋渡し」として活用できます。
- Strengths(強み):営業個人が得意とするスキル、顧客から評価される特長
- Weaknesses(弱み):苦手な行動、経験不足によるミスの傾向
- Opportunities(機会):市場拡大、顧客ニーズの新たな芽
- Threats(脅威):競合の攻勢、法規制や景気変動など外部要因
例えば、1on1や評価面談で「あなたの強みと市場の機会をどう結びつけるか?」と問いかければ、部下は単なる自己評価にとどまらず、環境に即したキャリア開発や行動計画を考えられるようになります。
AI活用例
SWOTは項目を埋めるだけで終わってしまいがちですが、AIを活用すれば「行動につなげる分析」に昇華できます。
📌 営業実績と顧客コメントからSWOT生成
以下の営業実績データと顧客フィードバックをもとにSWOT分析を作成してください。
・Strengths(強み)
・Weaknesses(弱み)
・Opportunities(機会)
・Threats(脅威)
各項目を3点以内で簡潔にまとめてください。📌 個人育成プランへの接続
AIにSWOT結果を入力させ、「強み×機会(SO戦略)」や「弱み×機会(WO戦略)」を出力。
次の行動計画や学習テーマの叩き台にする。
👉 SWOTは、営業個人やチームの現状を整理するだけでなく、「強みをどう機会に活かすか」までを考えさせる育成の土台となるため、AIを組み合わせれば、分析を行動プランに直結させやすく、形骸化を防ぐことができます。
6. TOWS(トウズ) 共通フレームワーク(実行)
歴史
TOWSは、SWOT分析の応用・発展形として1980年代に提唱されました。
SWOTで整理したStrengths(強み)/Weaknesses(弱み)/Opportunities(機会)/Threats(脅威)を単に列挙するだけでなく、要素を掛け合わせることで具体的な戦略オプションを導き出す手法です。
そのため「クロスSWOT」と呼ばれることも多く、経営戦略やマーケティング計画を策定する際に「次の一手」を考える枠組みとして使われています。
営業育成での使い所
営業育成の場でTOWSを使うと、部下の強みや課題を「どう活かすか/どう克服するか」まで具体化できるのがポイントです。
- SO戦略(Strengths × Opportunities):強みを活かして市場機会をつかむ→例:得意な提案力を活かし、新市場向けにソリューションを展開
- WO戦略(Weaknesses × Opportunities):弱みを改善しつつ市場機会を取り込む→例:ヒアリング力不足をトレーニングし、顧客ニーズ開拓に活用
- ST戦略(Strengths × Threats):強みを使って外部の脅威を和らげる→例:既存顧客基盤の強さを活かし、価格競争を回避
- WT戦略(Weaknesses × Threats):弱みと脅威が重なる部分を最小化する→例:提案スピードの遅さを改善し、競合優位性を確保
評価面談やキャリア相談の場で「SWOTをやって終わり」ではなく、「TOWSに基づいて具体的にどの戦略を選ぶか」を話せば、次の行動プランが明確になります。
AI活用例
TOWSは「組み合わせ思考」が肝ですが、AIに整理を任せると効率的に戦略オプションを出せます。
📌 SWOTからTOWS戦略を生成
以下のSWOT分析をもとに、TOWS戦略を導出してください。
・SO戦略(Strengths × Opportunities)
・WO戦略(Weaknesses × Opportunities)
・ST戦略(Strengths × Threats)
・WT戦略(Weaknesses × Threats)
各戦略を1〜2行で提案してください。📌 評価面談での活用
部下のSWOT分析を入力→AIがSO/WO戦略を具体的な行動案に変換。
「どの戦略を取るか」を上司と部下で合意し、KPIに落とし込める。
👉 TOWSは、SWOTを棚卸しで終わらせず、次の一手に転換する実践フレームであり、営業育成に使えば、部下の強みや弱みを行動計画に直結させられ、育成面談の「話して終わり」を防ぐ効果があります。
7. OODAループ(ウーダ) 補足フレームワーク(実行)
歴史
OODAループは、Observe(観察)/Orient(状況判断)/Decide(意思決定)/Act(行動)の4ステップで構成される意思決定フレームワークです。
1970年代にアメリカ空軍のジョン・ボイド大佐が、戦闘機の空中戦において「相手よりも早く意思決定を回すこと」が勝敗を分けるとして提唱しました。
その後、軍事領域から経営戦略や組織論に輸入され、特にVUCAのような不確実な環境下でPDCAに代わる有効な実行フレームとして紹介されることが増えています。
営業育成での使い所
営業活動は想定外の出来事がつきものです。
OODAを育成に取り入れることで、「考える→試す→修正する」短サイクルの行動習慣を部下に根づかせられます。
- Observe(観察):顧客の反応や市場の変化を捉える
- Orient(状況判断):自社の戦略や顧客の文脈に照らして整理する
- Decide(意思決定):次の一手を決める
- Act(行動):すぐ試して反応を見る
例えば、OJTで「顧客が予想外の質問をした」ときに、PDCA的に「次回改善」ではなく、OODA的にその場で意思決定して行動することを訓練できます。
AI活用例
OODAは「どの段階が弱いか」を特定するのが難しいですが、AIを使えば分析が可能です。
📌 商談ログをOODAで診断
以下の商談記録を、OODAの4ステップ(Observe/Orient/Decide/Act)の観点で分類してください。
各ステップに対応する発言を抜粋し、不足しているステップがあれば指摘してください。📌 振り返りの効率化
AIに「この営業はOrientが弱く、状況判断を飛ばして決断している」とフィードバックさせることで、育成ポイントが明確になる。
👉 OODAは「不確実な環境で素早く意思決定するための行動フレーム」であり、営業育成に取り入れれば、考えるだけでなく「試して修正する」実践力を高められ、VUCA時代に即した育成サイクルを作ることができます。
8. 営業育成に使える共通フレームワークのまとめ
営業育成の現場では、成果や行動を「個人の資質」にだけ結びつけてしまうと、対話が平面的になりがちです。
そこで役立つのが、VUCAやBANIのような環境認識フレーム、PESTや3Cのような思考整理フレーム、そしてSWOT/TOWSやOODAのような行動につなげるフレームです。
- VUCA/BANI→外部環境や不確実性を整理する
- PEST/3C→市場や競合、自社の立ち位置を俯瞰する
- SWOT/TOWS→個人やチームの現状を戦略に変換する
- OODA→不確実性に即応し、短サイクルで行動を改善する
重要なのは、理論を丸暗記してそのまま適用することではありません。
フレームワークは「万能の答え」ではなく、対話を助ける補助輪として使うものです。
営業育成の場では、状況に合わせて要素を組み替えたり、AIに下準備を任せたりすることで、実践的な効果を発揮します。
 無料相談
無料相談