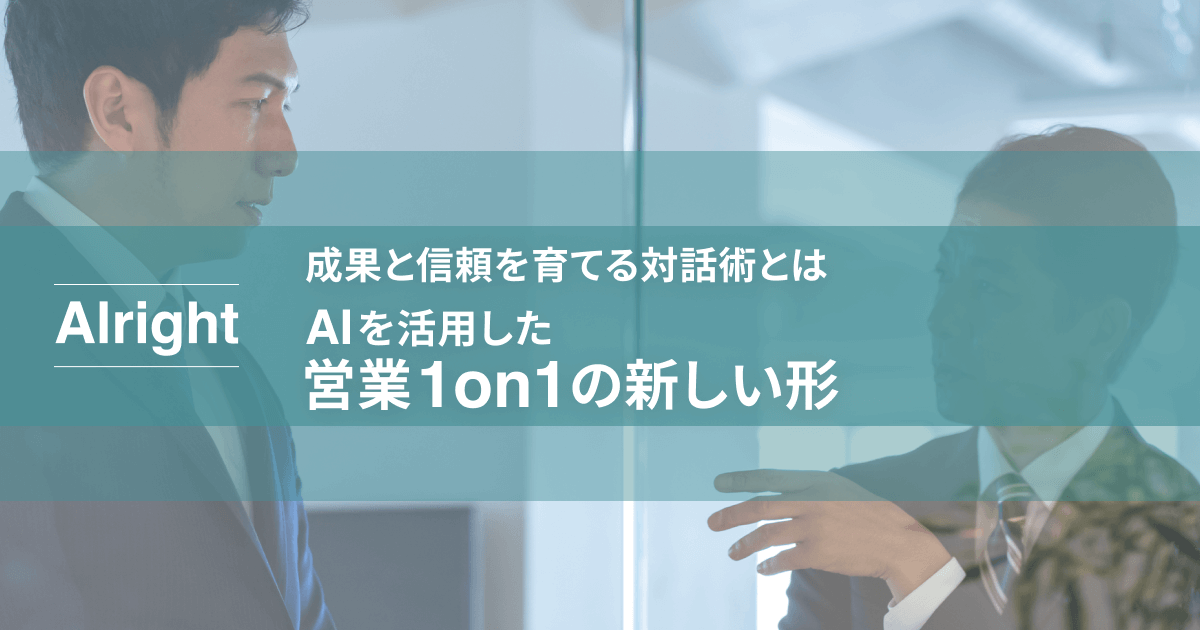なぜ今、営業現場で「1on1」が注目されるのか
営業マネジメントの現場は、いま大きな転換点にあります。
リモートワークの普及、Z世代の価値観の台頭、副業・ジョブ型雇用の浸透。
かつて当たり前だった「同じ場所・同じ時間・同じやり方」は、もう成立しなくなっています。
数字だけを追う管理や、会議室での一方的なフィードバックでは、人は動かない。
特に営業の現場では「何をどう頑張ればいいのか」を、個別に寄り添って引き出す仕組みが欠かせなくなっています。
そこで再び注目を浴びているのが 「1on1(ワン・オン・ワン)」。
上司と部下が定期的に向き合い、キャリアの悩みから日々の課題までをフラットに語り合う場です。
評価や査定ではなく、成長支援と信頼構築のための対話であることが特徴です。
「OJTで現場を鍛えればいい」「評価面談で十分では?」と思う方もいるかもしれません。
ですが、変化の激しい時代においては、それだけでは届かない部分が増えています。
1on1は、単なるトレンドではありません。
営業チームが成果を上げ続けるための、「次のマネジメント基盤」として求められているのです。
1. 1on1とは何か? 「定義とその進化する役割」
そもそも「1on1」とは?
1on1(ワン・オン・ワン)は、上司と部下が定期的に1対1で行う対話の場を指します。
一般的には25〜30分程度、週1回〜月1回といった頻度で実施されることが多いミーティング形式です。
重要なのは、これは「評価」や「査定」の場ではなく、成長支援と信頼構築を目的としている点。
「上司が一方的に教える」のではなく、「部下の言葉を引き出す」ことに価値があります。
OJTや評価面談との違い
- OJT(On the Job Training):現場でスキルを教える「訓練の場」
- 評価面談:一定期間の成果をもとに査定やキャリアを決定する「判定の場」
- 1on1:進捗や成果そのものよりも、「なぜそう感じているのか」「どう成長したいのか」を対話する「成長対話の場」
つまり1on1は、OJTや評価面談では拾いきれない領域を補う存在なのです。
営業現場における役割の進化
昔は「ちょっと話そうか?」と飲み会や帰り道で自然に行われていた対話。
しかしリモートや直行直帰の普及で、偶発的なコミュニケーションは激減しました。
そこであえて時間を確保し、意図的に「聴き合う場」を設計する必要が出てきた。
これが「1on1」という形で再定義され、今あらためて重視されている理由です。
1on1・OJT・評価面談の比較表
| 項目 | 1on1 | OJT | 評価面談 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 成長支援・信頼関係の構築 | 実務スキルの習得・即戦力化 | 成果や行動の評価・査定 |
| テーマ | キャリア・働き方・心理面・日々の課題 | タスク遂行方法・営業スキル | 目標達成度・評価基準 |
| スタンス | 傾聴・問いかけ・共創 | 指導・デモ・フィードバック | 判定・説明・納得形成 |
| アウトプット | 気づき・次の小さなアクション | スキルチェック・改善指示 | 評価シート・昇進昇格の判断 |
| 頻度・タイミング | 定期(週〜月単位) | 随時(案件・同行の場面ごと) | 定期(期末や半期ごと) |
| 関係性への影響 | 信頼関係の土台をつくる | 上司=指導者の色が強い | 上司=評価者としての色が強い |
| 注意点 | 評価と混同すると本音が出ない | 教える側の力量差が大きい | 一発勝負になりがち、緊張感が強い |
2. 営業現場における1on1の価値 「成長支援から離職防止まで」
「ただ話すだけで、本当に意味があるのか?」
営業マネージャーからよく聞かれる疑問です。
ですが、営業という成果プレッシャーの強い環境だからこそ、定期的な1on1がもたらす効果は非常に大きいのです。
1. 心理的安全性の確保
数字に直結しない不安や悩みは、放置されるとじわじわとモチベーションを削ります。
「この人には話せる」という安心感があるだけで、部下は自分の課題を言語化しやすくなり、結果的に行動も前向きになります。
2. 微修正によるロスの削減
営業活動はスピード勝負です。
- 見込み客の優先順位
- 提案内容の方向性
- 顧客ニーズの読み違い
こうした「ちょっとしたズレ」は、早めに修正すれば致命傷になりません。
週次や隔週での1on1があることで、ズレを大きくする前に立て直せるのです。
3. 自律性の促進
上司からの指示だけではなく、自分の言葉で「何をやるか」を表明する機会が増えると、人は行動への納得感を得ます。
この「自分で決めた感覚」が、営業現場における行動力と粘り強さを支える要素になります。
4. 離職防止・定着率向上
営業職は成果に直結するプレッシャーから、離職率が高い職種の1つです。
定期的にキャリアや働き方に関する思いを話せる場があると、「自分は見てもらえている」という感覚が生まれます。
それは組織への安心感となり、結果的に定着率を高めます。
まとめ
営業現場における1on1は、「成果を直接上げる仕組み」ではありません。
ですが、成果を生み出す「土壌」を整える仕組みとして、欠かせない役割を果たしています。
3. 形骸化を防ぐ運用デザイン 「続けやすく、意味ある1on1にするために」
1on1を導入したものの、次第に「なんとなく形だけ」になってしまうケースは少なくありません。
特に営業現場では数字や案件対応に追われやすく、時間が後回しになりがちです。
ここでは、1on1を形骸化させずに続けるための工夫を整理します。
1. 続けられる仕組みにする
- 所要時間:25〜30分を目安にする(短すぎると深掘りできず、長すぎると負担)
- 頻度:週1〜月1。現場の忙しさとバランスを見て無理なく設定
- 場所:オンライン・オフラインを柔軟に使い分ける
完璧さを求めず、「続けやすさ」を優先することが、定着の第一歩です。
2. 会話のバランスを意識する
1on1は「上司が話す場」ではありません。
部下が安心して話せる空気をつくるために、部下7:上司3を目安に会話比率を意識しましょう。
発言量をAIで可視化する仕組みを取り入れるのも有効です。
3. アジェンダの「型」を用意する
話題に困らないよう、あらかじめテーマの引き出しを準備しておくとスムーズです。
| 目的 | 話すテーマ例 |
|---|---|
| 進捗確認 | 達成状況・課題・アクションプラン |
| 顧客理解 | 顧客との関係性・課題認識の整理 |
| 実行障害 | 今抱えている悩み・困りごと |
| キャリア | 将来像・チャレンジしたいこと |
| 健康面 | ストレス・コンディション確認 |
「自由に話していいよ」よりも、一定の型がある方が安心して本音を出しやすいものです。
4. 記録と振り返りを欠かさない
その場の会話で終わらせず、要点やアクションをメモに残し、次回につなげましょう。
「前回こう話していたけど、今どうなった?」という一言が、部下にとっては「ちゃんと見てくれている」という信頼の証になります。
5. NGパターンに注意する
- 評価の話と混同してしまう
- 上司の独演会で終わる
- 雑談だけでアクションが決まらない
- 議事録を残さない
これらは1on1を「意味がない」と思わせる典型です。
あらかじめ避けるポイントを共有しておきましょう。
4. フィードバックとフィードフォワード 「過去から学び、未来へつなげる」
1on1の場でよく使われる技術に「フィードバック」と「フィードフォワード」があります。
似た言葉ですが、対象とする時間軸が違います。
フィードバックとは
- 対象:過去の行動や成果
- 目的:よかった点や改善点を明確にする
- 活用例:「先週の提案では、事前準備が顧客に伝わって好印象だった」「一方で、価格説明は少し曖昧だったね」
営業現場では、成功体験を再現可能にするための「振り返り」として有効です。
ただし「ダメ出し」と受け止められないよう、ポジティブな要素も必ずセットにすることが大切です。
フィードフォワードとは
- 対象:これからの行動や未来の可能性
- 目的:次の一歩を前向きに設計する
- 活用例:「次回は、価格説明を顧客の投資効果に置き換えて話すと、もっと響くはず」「次の訪問では導入後の未来像を一言で伝えてみよう」
未来志向のアプローチなので、部下にとっては行動を起こしやすく、心理的負担も少なめです。
両者をバランスよく取り入れる
- フィードバック:過去を振り返って学ぶ
- フィードフォワード:未来に向けて可能性を広げる
どちらか一方に偏るのではなく、両輪で使うことで1on1の対話がより建設的になります。
特に営業では、「振り返り」から「次の仮説」へつなげる流れを意識すると効果的です。
5. フレームワークを取り入れる 「一律対応から人に合わせるマネジメントへ」
1on1を効果的に進めるためには、「ただ話す」だけでなく、相手や状況に応じて関わり方を変える視点が欠かせません。
そこで役立つのが、マネジメントや心理学のフレームワークです。
SLII®(状況対応型リーダーシップ)
部下1人ひとりの成熟度に応じて接し方を変えるモデル。
- D1(初心者):経験不足→明確な指示が必要
- D2(成長途中):やる気はあるが自信不足→コーチングで支援
- D3(自律途上):能力はあるが迷いがある→寄り添い・共感
- D4(熟練):高い能力と意欲→委任して任せる
👉 1on1で「どの段階か?」を意識すると、適切な問いかけや任せ方が自然に見えてきます。
VUCA / BANI(環境変化のフレーム)
- VUCA:Volatility(変動性)/Uncertainty(不確実性)/Complexity(複雑性)/Ambiguity(曖昧性)
- BANI:Brittle(脆さ)/Anxious(不安)/Nonlinear(非線形)/Incomprehensible(不可解)
現代の営業環境は、不確実で変化が速いのが前提です。
「完璧な計画」ではなく、仮説と検証を短サイクルで回すために1on1を活用する、という発想が必要になります。
SCARFモデル(心理的安全の要素)
- Status(地位):自分が尊重されているか
- Certainty(予見可能性):先の見通しがあるか
- Autonomy(自律性):自分で選べているか
- Relatedness(関係性):仲間意識を持てているか
- Fairness(公平性):不公平感がないか
この5要素は、人が安心して本音を話せるかどうかを左右します。
例えば「定刻に始める」「アジェンダを事前共有する」といった小さな工夫で、Certainty(予見可能性)を高められます。
まとめ
フレームワークを取り入れることで
- 部下ごとの違いに応じた接し方ができる
- 環境変化を前提にした対話ができる
- 心理的安全性を高められる
つまり、1on1を「一律」から「個別最適」へシフトできるのです。
6. 営業1on1×AI活用の実際 「AIは静かな同席者、主役はあくまで人の対話」
AIは営業マネージャーの代わりに部下と話すわけではありません。
役割はあくまで準備・記録・振り返りを支える静かな補助者です。
ここでは、1on1の前後・実施中にどうAIを活用できるかを整理します。
Before(準備)
- 情報の整理:商談録音の文字起こし、CRMの更新、メール要点などをAIに要約させて「3分で読める材料シート」にまとめる
- テーマ候補の抽出:「最近の学び」「今の課題」「次の仮説」をAIに3行ずつまとめさせ、アジェンダ候補に
👉 マネージャーは「何を話すか」をゼロから考える負担が減り、本番は聴くことに集中できる
During(実施中)
- メモ支援:会話の要点をAIが「課題 → アクション → 担当 → 期日」の形に整理
- 問いのレコメンド:部下の発言ログをAIに分析させ、SLIIモデルを参考に「次に問うべきオープンクエスチョン」を表示
👉 会話に集中しながらも、見落としがちな切り口をAIが補ってくれる
After(振り返り)
- サマリ配信:その日の会話内容を30秒で読めるサマリにして部下に共有
- 小実験の提案:次回までに試せる具体的なアクションを2つに分解し、リマインドメールとして送る
👉 「対話で終わらない、行動につながる1on1」を後押しできる
Across(継続運用)
- ナレッジ化:本人が許可した内容を匿名化し、タグ付けして蓄積。類似課題が出た時に再利用できる
- メトリクス可視化:実施率・発話比率・アクション完了率をAIが自動で算出。形骸化の兆候を早めに発見できる
ポイント
AIを導入することで
- マネージャーは「雑務に追われる管理者」から「対話に集中できる支援者」へ
- 部下は「一方的に話を聞かされる」から「自分で気づきを得る主体」へ
役割がシンプルになり、1on1の質と回数を無理なく両立できるようになります。
7. 営業評価との関係性 「成長対話と査定をどう切り分けるか」
1on1が形骸化したり、本音が出なくなったりする最大の要因は、評価と混同されることです。
「どうせここで話したことが査定に影響するんでしょ?」と思われた瞬間、部下は防御的になり、対話の意味がなくなってしまいます。
評価面談と1on1を明確に分ける
- 会議体を分ける:評価面談は期末や半期単位で、1on1は週次や月次で定期的に。スケジュール上も別物に設定する
- 資料を分ける:評価シートと1on1の記録は混在させない。ログは成長支援のためだけに残す
- 目的を分ける:
— 評価面談:過去の成果をもとに「判定」する場
— 1on1:今の思いを共有し、未来に向けて「意味づけ」する場
AIログの扱いにも注意
AIを活用して記録や要約を残す場合も、評価には使わないことを明言しましょう。
- 保存範囲を必要最小限にする
- 機微な内容は伏字化・匿名化する
- 本人が同意したものだけ共有ナレッジ化する
👉 「ここで話したことは査定には反映されない」とルールを明示することで、安心して本音を語れる場になります。
線引きがもたらすメリット
- 部下は安心して「本当の課題」や「将来の希望」を語れる
- 上司は「数字に表れないシグナル」を早期に拾える
- 結果として、評価面談も「冷たい査定」ではなく「納得感ある振り返り」につながる
まとめ
1on1は、営業評価と一線を画した成長のための投資時間。
評価と混ざらないルール設計こそが、1on1の効果を最大化するカギなのです。
8. よくある課題と処方箋 「意味がない・話さないをどう防ぐか」
どんなに意義ある取り組みでも、実際に運用すると壁にぶつかります。
営業現場の1on1でもよく聞かれる課題と、その解決のヒントを整理しました。
1. 雑談で終わってしまう
- 課題:「今日は何話そうか?」で始まり、世間話だけで終わってしまう。
- 処方箋:事前にアジェンダや質問リストを共有しておく。最後に「次回までの小さなアクション」を必ず決める。
2. 部下があまり話さない
- 課題:本音をなかなか出してくれず、上司が一方的にしゃべってしまう。
- 処方箋:まず上司が自己開示すること。「私も昔、こういう失敗をした」と経験をシェアすると、安心して話しやすくなる。心理的安全性(SCARFの要素)を意識するのも効果的。
3. 上司の独演会になる
- 課題:アドバイスが多すぎて、部下が聞き役に回ってしまう。
- 処方箋:会話の比率を「部下7:上司3」を目安に。必要ならAIで発話比率を可視化し、自己チェックする。
4. 意味を見出せない
- 課題:「1on1をやっているけど、成果につながっているのか?」と疑問視される。
- 処方箋:SLII®などのフレームワークを活用し、部下ごとにアプローチを変える。1on1の目的は「直接成果」ではなく、「成果を出すための土壌づくり」と繰り返し伝える。
5. 評価に結びつくと誤解される
- 課題:「ここで話したことが査定に響くのでは?」と部下が疑心暗鬼になる。
- 処方箋:評価面談と1on1を明確に分けるルールを示す。記録やAIログは「成長支援目的に限定」と明文化する。
まとめ
課題の多くは「場の設計」と「上司の姿勢」に起因します。
あらかじめ典型的なつまずきを共有し、チーム全体でこう運用するを合意しておくことが、成功の第一歩です。
9. 1on1の小さな30分が、大きな成果を育てる
営業現場における1on1は、決して派手な施策ではありません。
しかし、週に1回の30分が積み重なれば、数字以上の変化を生み出します。
- 部下は「見てもらえている」という安心感から、本音を話しやすくなる
- 上司は「数字に出ないシグナル」を早期にキャッチできる
- 結果として、チーム全体の成長速度が加速する
AIの活用によって、準備・記録・振り返りといった作業負担は軽減できます。
だからこそ、人間同士が向き合う「聴く」「問いかける」「支える」に集中できるのです。
1on1は単なる面談でも査定の場でもなく、未来の行動につながる対話の仕組み。
今の環境だからこそ、あえて「意図的に」この場を持つ意味があります。
まずは来週、30分を確保してみましょう。
その小さな一歩が、営業組織の信頼と成果を大きく変えていくはずです。
 無料相談
無料相談